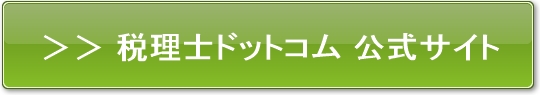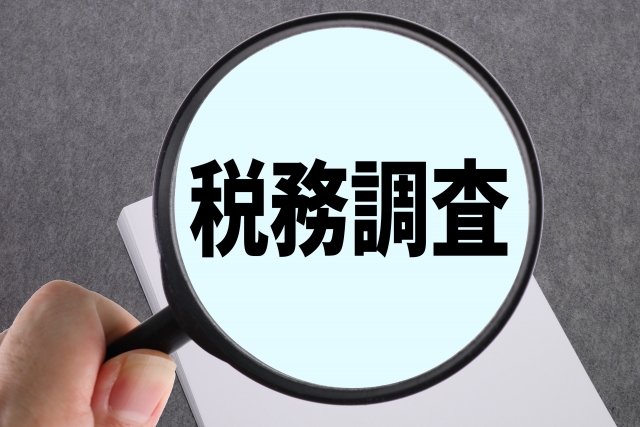本ページはプロモーションが含まれています。
水増し請求なぜバレる!税務調査でバレる理由、リスクを徹底解説!
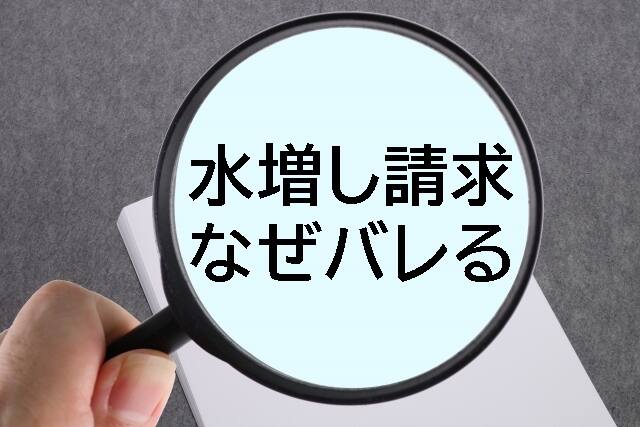
この記事では、水増し請求がなぜバレるのか?
税務調査でバレる理由、リスクを徹底解説しています。
水増し請求がなぜバレるのかですが、ほとんどが税務署による税務調査が入ったタイミングで水増し請求がばれています。
税務調査は、予告なし、または事前通知後に実施されます。
調査官は帳簿記録、領収書、関連文書などの財務情報を詳細にチェックし、不正な取引や架空の経費申告がないかを調べます。
このプロセスを通じて、経費の改ざんや不適切な請求などの水増し請求が発覚することがほとんどです。
水増し請求がバレる具体的な事例を紹介します。
ビジネスを運営しているなら、税務調査は避けて通れません。
もし、水増し請求をしていても、申告前なら今のうちに修正をしましょう。
税務調査が入ってからでは手遅れです。
すでに外注費の水増し請求をしていて税務調査の連絡が入っている事業者の方は、一刻を争います。
今すぐにでも、スポットで税務調査の立会いを依頼した方がいいでしょう。
税理士の立会いがないと、税務署にやりたい放題やられてしまいますよ。
税務署から税務調査の連絡が入ってからでも、スピード対応してくれる税理士事務所や、税務調査に強い税理士を紹介してくれる税理士紹介サービスがあります。
無料で相談できる税務調査無申告専門税理士を、3者紹介します。

一般の税理士が「税務調査」を経験するのは年に1回あるかないか。
多くの税理士は税務調査を苦手としていて、税務署の言いなりです。
その点、ここで紹介している税理士は税務調査立会のベテラン揃い。
税務調査のみの対応も可能です。
水増し請求がバレる具体的な理由
水増し請求が税務調査で発覚する主な理由にはいくつかあります。
ここでは、11の具体的な事例を紹介していますが、どれもバレるリスクが非常に高い行為であることがわかります。
証拠の不一致でバレる
下請け・外注費は、外注契約書、請求書、領収書、作業報告書、メールのやりとり、銀行取引記録など
の証拠を提出するよう求められるので、外注先との契約内容や支払い履歴に矛盾がある場合、水増し請求がバレる可能性があります。
*外注契約の条件が通常と異なったり、業界基準から大きく逸脱している場合など、契約期間や料金体系が他の契約と比較して異常に高い場合、水増しの疑いが生じます。
昔は、おかしいと思ったら「反面調査」で外注先に直接電話を入れたり、出向いたりして調べていました。
遠方の取引先には、所轄の税務署に紹介を依頼したりしていました。
KSKシステムでバレる
しかし、現在では、最新機能のデーター管理KSKシステムにより、架空会社、幽霊会社などは瞬時に把握でき、
取引先の申告状況や売上規模も確認ができ、異常な数値やパターンを自動的に検出し、取引の矛盾点を素早く調査することができるようになっています。
疑問点が見つかれば、なぜそのような支払いがあったのか、不正があるかどうかを徹底的に調べられることになります。
口裏を合わせてもバレる
もし、外注先と口裏を合わせていても、
外注先の帳簿に矛盾が見つかれば、外注先も同じ様に税務調査が入り、
芋ずる式に不正が発覚する可能性が高まります。
外注先は、先方からすると売上になるので、本当の金額より大きくして税金を余分に支払うことはしないので、下請け・外注費を水増ししていても、かなりの確率で露見します。
友達にお願いした「架空の外注先」は、もっと簡単にバレます。
いくら請求書や領収書を準備していても、その友達の名前の確定申告書をチェックし、会社員とわかれば、もう一発です。
反面調査は得意先にも調査が入る
「反面調査」で注意しなくてはいけないのが、仕入れ先だけでなく、得意先にも調査が入ることがあることです。
何もなくても、「何か悪いことでもしているのではないか?」と疑われることになって、取引に影響が出ることも考えられます。
できることなら避けたいのが「反面調査」です。
銀行調査でバレる
調査の内容に応じて、預金の動きを確認するための「銀行調査」も行われます。
税務署の調査官は、税務調査に入る前に、会社の3年間の決算書を横並びにしてチェックしているので、大きく増えた経費があると「何かあるな。」と思うので注意してください。
税務署へのタレコミでバレる
水増し行為は従業員や関係者などの内部告発や匿名の情報提供によりバレることがあります。
税務署員は内部告発や情報提供者からの情報を基に調査を行い、水増しの証拠を見つけることが以外と多く見受けられます。
横領がバレるタイミング
税務調査で、従業員のキックバックや横領が発覚することがあります。
本来なら従業員個人への課税になるケースですが、
この場合、会社としてはあずかり知らぬことでも、調査官はほぼ間違いなく会社の益金計上を求めてきます。
役員や経理担当、営業、資材担当などの従業員が、取引先への水増し請求や、売上代金を着服、在庫の横流しなどをしていた場合、
横領にあたるのですが、税務調査では会社に監督責任があると判断されます。
つまり、横領された金額は損失ではなく、損害賠償請求権として売上に計上する必要があるのです。
会社の収益と認定されれば、重加算税の対象になることもあるので注意が必要です。
場合によっては、国税不服審判所で争うことにもなりかねません。
キックバック:会社ぐるみ
キックバックは、会社ぐるみでおこなうこともあります。
建設業などによくあるのですが、仕事を受注した元請に内緒で元請の担当者にお金を支払うものです。
このお金は内緒のお金なので、当然経費として処理することはできません。
しかし、税務調査でバレた場合は、元請の売上となり、元請が過少申告を指摘され、重加算税が課せられることもあります。
この悪しき習慣はなかなかなくならないようですが、
もしこうなってしまったら、元請から取引を打ち切られれることも考えられます。
とにかく、キックバックには大きなリスクがあります。
関係者への質問でバレる
調査の過程で税務署員は、家族や従業員に質問をすることがあります。
証言や供述に矛盾や不正確な点があれば、水増しの実態が明らかになる可能性があります。
ただし、家族や従業員が税務調査の現場にいる場合です。
税務署調査官の周りをうろうろしていたらついでに質問されるかもしれません。
現場にいなければ、家族や従業員を呼び出して質問をするということはありません。
利益が少なすぎてバレる
「どうせ調査は来ないだろう」とたかをくくり、安易に「下請け・外注費」として架空経費を計上し、
確定申告の利益を少なくし過ぎても税務署に目をつけられます。
仮に申告書の扶養控除が奥さんと子供2人の4人家族の場合で、年間利益を200万円まで減額すると、
いったい4人家族で、どうやって生活しているの?となってしまい、簡単にバレてしまいます。
単純ミスによる水増し請求
単純なミスで経費を過大計上したことが、税務調査で発覚しても重加算税の対象にはなりませんが、
調査官に「単純な誤り」であることを証明する必要があります。
証明できない、もしくは説明しても調査官が納得できなければ、重加算税の対象になることもあります
売上の過小申告も、たとえば、作成された計算書から決算書に合計額を転記するときの単純な転記ミスでも、
「単純な転記ミス」であることを証明できなければ、重加算税の対象になります。
水増し請求以外の税務調査の調査項目

税務調査では下請け・外注費の水増し以外に下記の項目を優先して調べます。
- 売上計上のズレ、漏れ
- 接待交際費の中に、個人の経費が入っていないか
- 在庫計上は正確か
- 人件費、下請け・外注費に架空がないか
- 関連会社との取引きは適正か
- 役員退職金は適正か
- 前年と比べて大きく増えた固定費
- 車両や社屋など大きな金額が動いた買い物 などなど
一部をもう少し詳しく説明します。
売上計上のズレ、漏れ
売上の漏れも、飲食店や小売店などは調査官が事前にお店で飲食したリ、購入したりしてその時のレシートを保管しています。
その売り上げが、きちんと計上されているか確認します。
売上をごまかしたお金を個人の通帳に入金する人が多いですが、社長の個人の通帳も確認するので、おかしい入金はすぐにばれてしまいます。
銀行も税務署が照会をすれば、社長の了解を得なくても通帳を開示するので、丸わかりですよ。
領収書 偽造
領収書の水増しは、簡単にできることから、最も多く見られる手口です。
改ざん手口には、書き換える方法と、ニセの領収書を作成する方法があります。
前者は、インクや筆圧の違い、書き加えによる違和感などで、おかしな箇所は目につき見つけられると思った方がいいでしょう。
後者は、馴染みの店に偽装してもらったり、未使用の領収書を購入し使用するケースです。
これも、税務調査官は対象者の行きつけの店にも調査に入るため簡単に見破られます。
接待交際費の水増し
よくありがちなのが、家族旅行や、プライベートの食事、個人の買い物などを交際費に含ませる脱税行為です。
どこの会社でもよく目にするので、上手く隠したと思っても、バレると思っておいた方がいいでしょう。
旅費交通費の水増し
旅費交通費は領収書を発行しにくい経費なので、水増しが発覚しにくいです。
しかしETCの記録や宿泊記録、新幹線の搭乗記録など複数の事実を突き合わせることで、辻褄が合わなくなり発覚することがあります。
在庫(棚卸資産)過小申告
在庫を過小に申告する会社も多いですが、調査官もよくわかっているので、かなり詳しく調べてきます。
抜粋した商品の仕入れから販売までの流れを一つづつ見ていきます。
そこで、不正が発覚したら全在庫商品を対象に調べられることもあります。
社長のパソコンの中に、裏帳簿で正しい在庫表が発見されたらアウトです。
タイムカード改ざん
架空の人件費は、タイムカード、履歴書、銀行振込明細書、社会保険などで調べます。
アルバイトを多く使う会社ほど、詳しく調べられます。
内定調査
飲食業や宿泊業などのように、一般消費者を顧客層とする業種には内定調査が入ることがあります。
店舗付近で客の入りを確認したり、必要に応じて担当官が客を装って入店し従業員数や客単価を調査します。
その調査をもとに売上予想を立て、内偵による収支予測と申告内容との間に乖離があるかをチェックします。
外観調査
社長の自宅を訪れ、過度に豪華でないか、修繕痕はないか、自動販売機を設置しているかなどを調べたりします。
これは、社長個人の支出を会社の損金として計上していないかの確認です。
水増し請求のリスク
水増し請求のリスクについて説明します。
追徴課税のリスク
水増し請求を行うと、税務調査によってこの不正が発覚した場合、追徴課税が課されるリスクがあります。
具体的には、実際にかかった経費よりも多くの金額を経費として計上していた分について、税務署から追加で税金を請求されます。
追徴課税は単に未払いの税金を支払うだけでなく、遅延利息や罰金が加算されることも一般的です。
このような追加費用は、企業の財務に重大な影響を及ぼす可能性があります。
詐欺罪のリスク
水増し請求は、単に税金の問題に留まらず、詐欺罪に問われるケースもあります。
水増し請求を行うことは、故意に虚偽の情報を提供する行為に当たり、これが刑事罰の対象となる可能性があります。
詐欺罪に問われると、金銭的なペナルティのほかにも、社会的な信用失墜や、最悪の場合、実刑判決を受けることも否定できません。
企業としての信頼性が大きく損なわれ、ビジネスチャンスの損失にも繋がりかねません。
以上のように、水増し請求は税務署にバレるリスクが非常に高く、発覚した場合のリスクも重大です。
税務調査だけでなく、法的な責任も重大であるため、正直で透明性のある経理処理を心がけることが最も重要です。
水増し請求を防ぐための対策
水増し請求を防ぐための対策について説明します。
経理の透明性を確保する
水増し請求や経費の不正を防ぐためには、まず経理の透明性を確保することが非常に重要です。
経理の透明性を高めるためには、企業が全ての金融取引記録を正確に保持し、常に更新する必要があります。
また、領収書や請求書をデジタル化し、関連する文書を簡単に検索およびアクセス可能にする電子システムの導入が有効です。
これにより、経理プロセスが透明になり、不正が防げます。
さらに、外部の会計監査を定期的に実施することも、透明性を保つ一つの手段です。
専門の監査人による厳正なチェックを通して、経理処理の正確性を保証し、問題があれば早期に対応できます。
不正を防止・発見するシステムを導入する
不正を効果的に防止・発見するために、最新の技術を利用したモニタリングシステムを導入することが推奨されます。
例えば、人工知能(AI)を利用したソフトウェアは、異常な取引パターンを自動で検出し、アラートを発することができます。
これにより、不正行為が企業内で発生した場合に迅速に対応することが可能です。
また、従業員に対する継続的な教育とトレーニングも重要です。
不正行為を防ぐためのポリシーと手順を従業員全員が理解し、それを徹底すれば、不正行為の発生リスクを大幅に下げることができます。
定期的なワークショップやセミナーを開催し、正しい経理処理方法や不正行為の影響についての意識を高めましょう。
これらの対策を実施することで、水増し請求や経費の改ざんといった不正を未然に防ぎ、企業の信頼性を守ることが可能になります。
経理の透明性を確保し、先進的な不正防止システムを導入することが、不正リスクを最小限に抑える鍵となります。
税務調査の立ち会いはスポットでも税理士に依頼できる
顧問税理士がいない会社でも、税務署から税務調査の連絡が入ってからでも、税務調査に強い税理士に税務調査の立ち合いをスポットで依頼することができます。
顧問税理士がいる会社でも、税務調査の経験が少ない税理士だと、税務署の言いなりで、ぜんぜん力になってくれないということもあるので、
税務調査の立ち合いだけを税務調査に強い税理士に頼むこともできます。
税務調査が無事すんだ後でも、税理士を変更する必要はありません。
その場合の気になる料金を紹介します。
税務調査 スポット税理士 料金
税務調査に強い税理士の料金は、「1日4〜6万円 × 調査日数」、
もしくは1時間1万円が料金の相場です。
あとで紹介しますが、法人、個人事業主問わず立会料は1日1万円ポッキリ、成功報酬なしという明朗会計の税務調査専門税理士もいます。
◆最安値:無料
会計ソフト大手の「freee」では、年額39、800円(税抜)の「プレミアムプラン(個人事業主向け)」サービスに、税務調査サポート補償を加えました。
【補償内容】
(1) 税務調査の際、無料で税理士を紹介。
(2) 税務調査の際にかかる税理士の立会費用を補償。
・支払限度額 : 50万円
・免責金額 : 0円
※事前準備、当日の立会等にかかる費用を負担。(一日当たり10万円、1時間当たり1万円が限度)
ただし、対象者が故意、重大な過失または法令違反を行なっている場合や、
確定申告期間内に正しく確定申告を行なっていない場合は対象外になります。
どの税理士でもですが、税務調査後に修正申告が必要になった場合は、修正申告料金が10万円〜20万円が追加でかかります。
顧問税理士なら税務調査の立ち合いも顧問料の中に含まれていると思われるかもしれませんが、
一般的に通常の顧問契約内容には、税務調査への立ち会いは含まれていません。
ですので、税務調査に強い税理士にスポットで依頼した場合と、支払う料金はほとんど変わらないです。
ただし、税務調査前の書類の準備とか、税務相談などは、別途3万円〜5万円の料金が掛かりますが、
顧問税理士の場合は顧問契約の中に含まれていることが多く請求されることは少ないです。
もちろん、契約内容によって料金は異なるので、後で思わぬ請求をされるよりも事前に確認しておいた方がいいでしょう。
税務調査に強いスポット税理士の探し方
税理士と顧問契約をしているのなら、税理士が税務調査に立ち会ってくれます。
しかし、ここで税務署の言うとおりに従うのか、問題はないと筋を通すことができるのか税理士の力量が問われることになります。
まだ、税理士と契約していなければスポットで税務調査の時だけの対策、立ち合いをお願いすることができます。
ネットで簡単に調べることができますが、中には「税務調査に強い」とうたいながら、
まったく実績がない税理士もいるので注意が必要です。
税理士は近場の税理士に依頼
税務調査は、調査当日の立ち会いだけで済むことは稀で、事前に何度か打ち合わせが必要になることがほとんどです。
また、調査後には税務署との折衝が必要になる場合もあります。
そのため、税理士に依頼する場合には、遠方の場合はフォローが行き届かない可能性があるため、できるだけ通いやすい距離にある事務所を選ぶほうが望ましいでしょう。
税理士事務所のホームページを一つずつ調べるのもいいですが、
個人で希望する税理士を探すことは難しいのと、緊急を要するので、税理士探しは税理士紹介サービスを利用するのがおすすめです。
税務調査専門の税理士紹介サービス
おすすめは税務調査の立ち合い経験豊富な税理士の紹介に特化した大原政人税理士事務所と「税務調査立会ドットコム」です。
大原政人税理士事務所
大原政人税理士事務所は、税務調査無申告専門税理士で、自身も税務調査を受けた経験がある税理士本人が対応します。
スピードが勝負!
急な税務調査にも対応します。
相談は平日夕方以降、土日祝日も対応。
ただし、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の1都3県とエリアが限定されます。
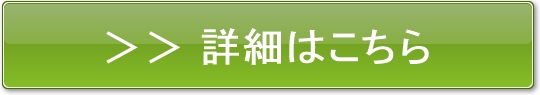
「税務調査立会ドットコム」税理士紹介サービス
「税務調査立会ドットコム」は、法人・個人事業主問わず、急な税務調査でも税務調査対応の専門税理士が1日1万円ポッキリで立ち合ってくれる税理士紹介サービスです。
費用は税務調査に要した日数分だけの請求で、成功報酬等のグレーな請求はありません。明朗会計です。
ただし、「税務調査立会ドットコム」も対応エリアが限られています。
(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の1都3県)
平日の夕方以降や、土日祝日も相談を受け付けているので、いつでも連絡を取ることができます。
税務調査立会ドットコムは相談は無料。
税務調査の連絡があってからは、1日が命取りになることもあります。
まずは、問合せしてみませんか?
基本プラン 10,000円
↓税務調査に要した日数分だけのご請求!↓
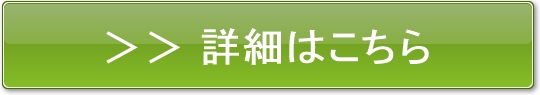
上場会社が運営の業界トップクラスの税理士紹介サービス
上記で紹介した2者は、地域が限られています。
以外の地域でおすすめなのは、国内最大の税理士の登録数で、相談件数、マッチング件数がトップクラスの税理士ドットコムです。
数多い税理士紹介サービスの中で、唯一の上場企業が運営していて信頼できるのと、
24時間受付けているので、素早い対応を取ることができます。
要望を伝えるだけで、近隣でスポットの税務調査に対応できる税理士を紹介してもらえます。
早ければ、相談したその日に紹介してもらえることもあります。
↓税理士の登録数 業界最多↓