

本ページはプロモーションが含まれています。
相続税をゼロ円にする方法。裏技ではありません。生前対策、相続発生後対策
相続税には、正当な方法で税金を節税し、相続税をゼロ円にする方法があります。
これは合法的な手法であり、裏技ではありません。
実際、相続税をゼロ円にするための節税方法は、相続が発生した後でも利用できます。
相続税の節税方法は多岐にわたりますが、特に相続発生後に実施できる方法を中心に解説します。
誤った方法を選ぶと、逆に多額の税金を支払うことになってしまうので注意が必要です。
相続税の基礎控除額
まず、基本である相続税の基礎控除額を抑えておきましょう。
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
つまり、遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ相続税はかからないので、別段、相続税対策をする必要はありません。
相続税の課税対象外となる財産
相続や遺贈によって取得された財産でも、相続税の課税対象外となる特定の財産があります。
- 日常礼拝をするための物品
墓所や仏壇、祭具など、日常的な礼拝に使用される物品 - 生命保険金
生命保険の受取人が相続人である場合、受け取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」 - 死亡退職金
相続人が死亡退職金を受け取った場合、そのうち「500万円×法定相続人の数」 - 債務や葬式費用
被相続人が生前に負っていた債務や葬式費用
「相続発生後」にできる相続税対策
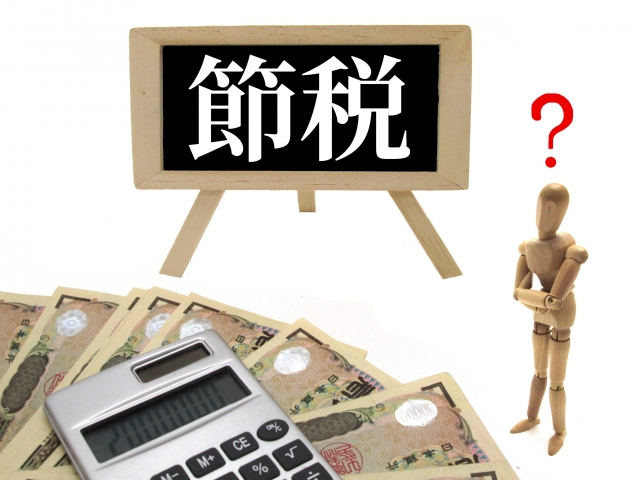
相続税の節税は「生前」に行うことでより効果的になりますが、十分な生前対策を行う前に相続が発生してしまった、というケースも少なくありません。
「相続発生後」でも実施可能な相続税節税対策
- 葬儀費用を増やす
- 適用できる税額控除制度を探す
- 土地を分筆し評価額を下げる
- 相続税申告の経験が豊富な税理士を探す
葬儀費用を増やす
告別式やお通夜などの葬儀費用は、遺産総額から差し引くことができるため、相続税額を減らすことができます。
ただし、香典返しに使った費用や生花・お供えにかかる費用などの、葬儀と直接関係ないものは控除対象になりません。
適用できる税額控除制度を探す
税額控除は、相続税額から直接差し引かれるため、相続税を大幅に減額することができます。
控除額を計算した結果、税額がゼロまたはマイナスになる場合、相続税はゼロとなります。
ただし、相続税がゼロになるためには、相続税申告時に適切な手続きを行う必要があります。
控除の適用を受けるためには、申告書類や必要な書類を提出するなどの手続きが必要です。
忘れずに手続きを行いましょう。
- 贈与税額控除
過去に贈与された財産に対して支払った贈与税額を差し引くことで、相続財産の評価額を減らす控除 - 配偶者の税額軽減
結婚している場合に相続税の納税額を軽減するための控除 - 未成年者控除
未成年の子供が相続した場合に相続税の納税額を軽減するための控除 - 障害者控除
身体的な障害や精神的な障害を持つ人々に対して相続税の納税額を軽減するための控除 - 相次相続控除
同一の相続人による連続した相続が発生した場合に、相続税の納税額を軽減するための控除 - 外国税額控除
海外で支払った相続税や贈与税の額を、日本の相続税から差し引くことで重複課税を回避するための控除
土地を分筆し評価額を下げる
相続財産に含まれる土地を分筆することで、土地の評価額を下げることができます。
土地の評価額が低くなると、相続税の納税額も減少します。
ただし、分筆には法的な手続きや費用がかかるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続税に精通した税理士を探す
相続税申告では、土地などの現預金以外の財産を相続した場合、相続税に精通した税理士に助けを求めることが重要です。
特に「土地」は元の価格が高い場合が多く、正確な評価額の補正の有無によって相続税の納税額が大きく変わってきます。
ただし、土地の評価に関する知識は税理士であっても、土地評価や相続税に関する実務経験がなければ正確な計算を行えないこともあります。
そのため、相続税を最大限に節税するためには、「相続税申告の経験が豊富な税理士」のサポートが不可欠です。
同じ広さの土地でも、形状や周辺環境などの条件によって評価額が異なるため、適切な補正を行うことが重要です。
以下は、評価額が減額される土地の例です。
- 広い地面積を持つ宅地
- 鉄道の近くに位置する土地
- 通路のない土地
- 傾斜のある土地
- 高圧線が通っている土地
- 不規則な形状の土地
- 忌み地とされる土地
- 庭に神社や祠がある土地
- 建築制限線に沿っている土地
- 境界が曖昧な土地
相続税の生前対策
相続税の節税を考える上で重要なのは、「生前」に対策を行うことです。
以下は相続税の節税対策の一部です。
- 非課税制度を活用する
・生前に財産を子や配偶者などの相続人に移動(贈与)することで、相続時の遺産額を減らし、相続税の節税につながります。
・年間110万円を超える贈与は贈与税がかかるため、贈与の方法を工夫する必要があります。
生前贈与でも、あえて贈与税を支払った方が節税できる場合もあります。
その境目はおおむね資産が2億円以上ある場合です。 - 暦年贈与
・毎年110万円までの贈与は非課税です。
毎年、同じ時期、同じ金額を生前贈与していると、定期贈与とみなされ贈与税がかかることがあります。
税務署できちんと承認してもらうためには、司法書士に頼んで「贈与契約書」を作成してもらう必要があります。
- 相続時精算課税制度
・相続時の贈与であれば、2500万円まで非課税です。 - 配偶者へ自宅を贈与する
・配偶者への贈与には、2000万円までの非課税枠があります。 - 結婚や子育ての資金を一括贈与する
・結婚や子育てに必要な資金の贈与は、1000万円まで非課税です。 - 子や孫へ教育資金を一括贈与する
・教育資金として一括で贈与する場合、1500万円まで非課税です。 - 子や孫へマイホーム購入資金を援助する
・住宅の取得や建築に必要な資金の贈与は、1000万円まで非課税です。 - 生命保険を活用する
・法定相続人の人数に応じて、死亡保険金の非課税枠が設けられています(1人につき500万円)。 - 祭祀財産を生前に購入
・お墓などの祭祀財産は原則として非課税です。 - 養子縁組をする
・養子縁組をすると、非課税枠が1100万円増えます。
一部をもう少し詳しく説明します。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、特別控除枠が合計2500万円まで設けられており、この枠内での贈与は贈与税が課されません。
贈与された財産は、将来価値が上がる可能性がある場合でも、贈与時の価額で課税されるため、相続時の値上がりした価額では課税されません。
この制度を活用することで、相続税の節税が可能です。
また、収益を生む財産(例えば賃貸物件や高配当株など)を贈与することで、相続人はその財産から家賃収入や配当を得ることができます。
さらに、受贈者の財産も増えていくため、相続人としての経済的なメリットもあります。
相続時精算課税制度を活用することで、被相続人が健在なうちに相続人と話し合いを行い、遺産の分配を円滑に進めることができます。
これにより、相続に関する争いや問題を未然に防ぐことができるため、家族間のトラブルを防止する上でも有効です。
養子縁組をする
養子縁組と言っても、他人を養子にすればトラブルの元ですから、養子縁組は孫を戸籍に入れるのが無難です。
養子縁組することで、相続税がかからない基礎控除額が600万円増えます。
1億5千万円の資産を子供1人と2人で相続する場合では、相続税は1,000万円以上節税できます。
相続財産だけでなく、生命保険の受取でも受取人が1人増えることで、500万円非課税枠が広がります。
900万円の保険金が入るとすると受取人が1人だと400万円に相続税がかりますが、孫が1人養子になることで、相続税はゼロになります。
不動産の対策をする
不動産に対する対策は、相続税の節税において重要な要素です。
以下に具体的な不動産対策をご紹介します。
- 現金を不動産に変える
・現金を不動産に投資することで、相続時の財産評価額を下げることができます。 - 更地に賃貸物件を建てる
・空き地を活用して賃貸物件を建てることで、不動産の収益性を高めることができます。相続時の評価額も土地のみとなるため、相続税を節税できます。 - 空き家を賃貸物件にする
・空き家を賃貸物件として活用することで、相続時の評価額を下げることができます。
空き家を有効活用することで、不動産の収益性を向上させることも可能です。 - 不動産管理会社を設立し財産を移行する
・不動産管理会社を設立することで、不動産資産を移行し、相続時の評価額を下げることができます。
不動産管理会社の設立により、収益性の向上や資産の有効活用も図ることができます。 - 「小規模宅地等の特例」を利用する
・「小規模宅地等の特例」は、住宅用地や農地など特定の条件を満たす不動産に対して、評価額の一部を軽減する特例です。
この特例を利用することで、相続時の評価額を抑えることができます。
以上が不動産に対する相続税節税の対策です。
ただし、具体的な対策の適用や節税効果は個別の状況や法律の変更によって異なる場合があります。
相続税の節税に関しては、専門の税理士や相続対策の専門家と相談することをおすすめします。
相続税をゼロ円にする相談は税理士へ
これまで紹介した節税対策は、自身で行うことも可能ですが、
相続税の節税を考える際には、税理士に相談することがおすすめです。
税理士は、相続税に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。
特に、相続税に精通した専門の税理士を選ぶことが大切です。
相続税に関する知識や経験が豊富な税理士は、個々の状況に応じた最適な節税対策を提案してくれます。
信頼できる税理士との相性も重要ですので、自分に合った税理士を選ぶことが重要です。
相続税申告では、個人の財産や家族の事情についても話し合うことがあります。
そのため、税理士とのコミュニケーションや信頼関係は非常に重要です。
お互いに話しやすい雰囲気があり、相談しやすい関係を築くことが大切です。
相続税に強い税理士の探し方
ここまでで紹介したように、相続税はとても複雑です。
また、毎年「税制改正大綱」が発表されて税法が変わります。
ですので相続税に精通している税理士に依頼しないと、相続税を余分に支払うことなります。
実は税理士は、「相続税法」を勉強していない税理士が多いのです。
エッツ!どういうこと? と思われるでしょうが真実なのです。
税理士の試験科目は11科目あるのですが、選択制で11科目のうち5科目を受験し合格すれば税理士になれます。
「相続税法」は選択科目です。
現実、選択科目で「相続税法」を受験する税理士は10%しかいないのです。
例えば、県で5本の指に入るという有名税理士が、土地の評価で単純なミスをして相続税を約1,000万円も余分に支払うことになったことがあります。
もっと大きなクレームの事例では、2000坪という広大な土地の相続で、1億9000万円の相続税を余分に支払うことなった事例もあります。
前者は、「小規模宅地等の特例」適用のミスで、後者は「広大地評価」の特例を見逃がして起こった事例です。
このように、ただ有名、事務所が大きいだけでは相続税を任せる判断材料になりません。
税理士事務所を構えながら、一度も相続税を取り扱ったことが無いという税理士がほとんどなのです。
相続税に強い税理士にお願いする
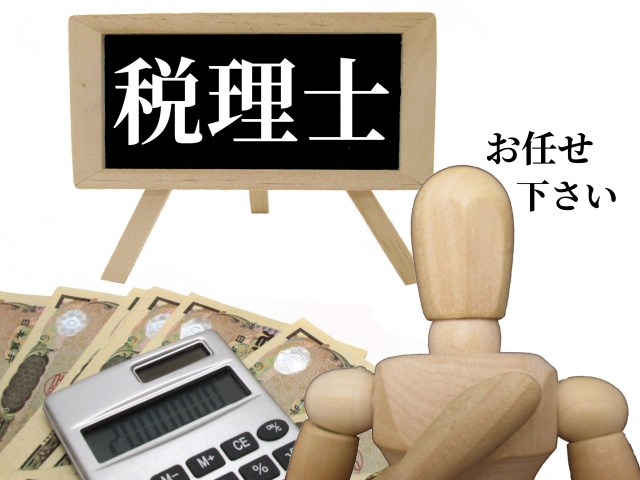
ではどうすればいいのか?というと、試験で「相続税法」の科目を受験し合格した人で、相続税を専門に取り扱っている経験豊富な税理士に頼むことです。
ただ、どの税理士が相続税に強いのかはホームページを見てもよくわかりません。
どこも、相続税を取り扱っているとPRしているからです。
こんな時には、税理士紹介サービスに依頼するのが一番です。
経験豊富で実績がある税理士を紹介してもらえます。
税理士とあなたの間に税務専門のコーディネーターが入り、聞きにくい「相続税法」試験のことや今までに相続税を取り扱った件数も確認してくれます。
1人だけでなく、希望すれば複数の税理士を紹介してもらえます。
断るときも、コーディネーターが断ってくれるので気まずい思いをすることはありません。
しかも、何人紹介してもらっても無料なのです。
数多い税理士紹介サービスの中でおすすめなのは、業界唯一の上場企業が運営する「税理士ドットコム」です。
登録税理士数、問い合わせ件数も業界最多です。
【関連記事】 税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
税理士紹介サービスは税理士ドットコム以外にもたくさんあります。
税理士ドットコム以外でも、探したい、相談したいという方はこちらをご覧ください。
> 税理士紹介サイトどこが良いか、おすすめを独断と偏見でランキング
> 相続に強い税理士の選び方!税理士、信託銀行に騙されるな!

