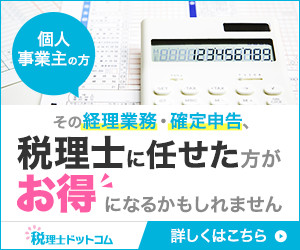本ページはプロモーションが含まれています。
経営セーフティ共済 裏ワザ!節税しても決算書では利益が増える裏技

ここでは、経営セーフティ共済 裏ワザを2パターン紹介しています。
1つは多くの方が説明している経営セーフティ共済の掛け金を損金にして節税するという裏ワザですが、
その方法では節税はできても決算書では利益が減ってしまいます。
2つ目の経営セーフティ共済 裏ワザは、節税しても決算書では利益が増えるという裏ワザです。
これは、どこも紹介していないやり方です。
利益が増えたら節税にならないのではと心配しないでください。
税金が増えることはありません。
しっかり節税できてるのに決算書の利益が増えるのです。
決算書の利益が増えるということは、銀行から融資も受けやすくなります。
あなたの会社も経営セーフティ共済に掛金を掛けているのならぜひ、このやり方で節税しながら決算書の利益を増やしてみてください。
経営セーフティ共済は節税の他に、取引先が倒産して資金繰りに困ったときは、預けていた共済金の10倍(最大8,000万円)の資金を無担保・無保証人ですぐに借りることができるのも特徴です。
他にも小規模企業共済での節税、資金繰り対策の方法や、旅費規程を作ることで節税する方法。
赤字の資金繰りを改善する方法。
赤字でも融資が受けられる、融資を受けやすくする裏技もここでは紹介しています。
経営セーフティ共済 裏ワザ
メリット
節税
経営セーフティ共済の裏ワザというと、利益が大きい年に掛金を前納して積み立てることで節税し、
赤字が見込まれる年に解約して収入として計上し、決算数字をよくみせるというのが一般的です。
倒産防止共済には12ヶ月分の前払い制度があるので、都合24ヶ月分、最大480万円を1年間で積み立てることで経費計上し節税することができます。
所得が500万円の場合、1年分の上限金額240万円を経費として計上することで、所得税と住民税あわせて約65万円の節税効果があります。
無担保・無保証人で借入ができる
節税とは関係ないですが、経営セーフティ共済の最もおすすめな理由は、無担保・無保証人で掛金の10倍まで借入ができることです。
先行きが予測できない時代において、連鎖倒産のリスクや経営難などの万が一に備えることができます。
デメリット
解約手当金は利益
掛金を積み立てて節税するのはともかく、
経営セーフティ共済を解約して収入として計上するというのは、受け取った解約手当金は、退職金のように税制上の優遇が無いので、単に税金の繰り延べをしているだけということです。
ですので、解約すれば解約金に税金がかかります。
出口戦略が必要
経営セーフティ共済の節税効果を高くするためには、「いつからいくら積立をするのか」「いつ解約をするのか」、
開始だけでなく、出口戦略をしっかり練ったうえで利用しないと効果の最大化ができません。
元金が減ってしまう
40ヶ月程度、継続加入すれば解約返戻金が100%戻ってくるので損はしませんが、
40ヶ月未満で解約してしまうと、受け取る解約手当金が掛金の総額を下回るということは知っておかないといけません。
掛金変更
業績がよくない時は、解約するのではなく毎月の掛け金を減額して1万円でも5千円でもいいので引き続きかけ続けることで目減りを防ぐことができます。
毎月の掛金は5,000円まで5,000円単位で減額することができます。
掛金月額変更申込書を中小機構のホームページからダウンロードして、
必要事項を記入したら登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に書類を提出します。
5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に書類が届けば、同月から減額された金額が引き落とされます。
6日以降に届いた場合、同月は変更前の掛金で引き落とされますが、差額が、翌月以降の掛金で調整されます。
経営セーフティ共済 裏ワザ:節税しながら利益を増やす
取引先の倒産によって連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐ、中小機構の経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の掛金を経費ではなく資産に計上することで利益を増やすことができます。
経営セーフティ共済の掛金は月5000円から20万円の間で設定できますが、多くの会社は保険料として損金(個人事業主の場合は必要経費)に計上しています。
損金に計上しているから、節税になるのに、資産に計上すれば節税にならずに税金が増えてしまう。
と考えてしまいますが、損金、資産のどちらに計上しても納める税金は変わりません。
資産計上したあと法人税の申告書で損金に計上できるからです。
税金が同じであれば、決算書の見た目を考えるなら、資産計上したほうが良いに決まってますよね。
経営セーフティ共済の掛金を経費にすると利益が減り、資産計上すれば利益が多く見えます。
こうすることで、決算書を見る銀行の評価が上がり資金調達する際に有利に働きます。
ただし、資産計上したあと法人税の申告書で損金にすることを顧問税理士に忘れないように処理してもらってくださいね。
経営セーフティ共済 法人成り
経営セーフティ共済は、個人事業主が法人成りした際に引継ぎをするか、解約するかの選択をすることになりますが、
法人成りした際に解約をすると解約金に税金がかかります。
無駄な納税を避けるためにも引継ぎをすることをおすすめします。
ただし、加入するには法人成りから3カ月以内に申し込む必要があります。
事業の法人化に伴い、共済契約を引継ぎする場合の必要書類は、「中小機構」のホームページからダウンロードすることができます。
必要書類に記入したら、登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に書類を提出します。
手続き完了後、中小機構から新たな『共済契約締結証書』が送付されます。
小規模企業共済の裏ワザ
節税、資金繰り対策では経営セーフティ共済の他に小規模企業共済があります。
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主などのための退職金制度です。
小規模企業共済は、常時使用従業員の数が20人以下の個人事業主または会社などの役員が加入することができます。
掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で設定でき、払い込んだ掛金の全額が所得控除の対象となります。
課税される所得金額が1,000万円の場合、掛金月額が5万円だとすると、262,200円が節税できます。
前納制度もあり、最大24カ月分の控除を同じ年に受けることができ、
掛金が最大額の場合は、70,000万円×24カ月=168万円が控除対象になります。
また、小規模企業救済を活用すれば、積み立てた掛金からお金を借りることができます。
最高2,000万円の融資も可能です。
保証人、無担保、審査不要で借入れの回数制限もなく、低金利(0.9%または1.5%)で貸付けを利用できます。
資金繰り悪化時には、特例緊急経営貸付けを利用すれば、無利子で借りられるケースもあります。
「小規模企業共済」と「中小企業共済」の違い
正確には、「小規模企業共済」は「小規模企業共済制度」、
「中小企業共済」は「中小企業退職金共済制度(中退共)」と言います。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主、共同経営者、会社等の役員を対象とした経営者の退職金共済制度。
中小企業退職金共済制度は、中小企業の従業員を対象とした退職金共済制度です。
旅費規程を作って節税
就業規則に出張旅費規程を整備することで、出張に対して日当を支給することができます。
その日当は給与とか役員報酬の一部とみなされないので所得税がかかりません。
出張が多い会社だと全然金額が違ってきます。
ただし、日当の金額は社会通念上妥当な金額にする必要があります。
また、従業員が増えてくると社長だけという訳にはいかなくなるので、他の部長とか課長、社員にも支払わなくてはいけません。
役職ごとに金額に違いをつけることはできます。
一人社長で出張が多いなら、ぜひとも取りいれたい節税方法です。
赤字で資金繰りが悪化しても倒産しない!
ここからは、赤字の資金繰り改善。赤字でも融資が受けられる。融資を受けやすくする裏技についてお話をしていきます。
東京商工リサーチのデータでは、2020年に倒産した会社のうち、倒産直前の決算が最終赤字だった会社は53.2%。
残りの約半分は、黒字であり、負債よりも資産のほうが多かったのです。
この数字からわかることは、会社は赤字や負債が原因で倒産するわけではないということです。
赤字は危ない? 負債は怖い?
潰れる会社は、運転資金がない、有利子負債(利息を付けて返済しなければならない借金)の利息を払う現金が尽きた会社なんです。
しかし、会社が赤字でも、資金繰りが悪化しても銀行から融資を受けることができれば倒産することはありません。
赤字で資金繰りが悪化しても融資を受ける方法
会社が赤字の場合、資金繰りが悪化しても銀行から融資を受けることはなかなか難しいです。
でも、会社が赤字でも銀行から融資を受けることができる会社はあります。
そんな会社には特徴があります。
あなたの会社も次に記載する特徴に合致していれば、赤字でも銀行から融資を受けられる可能性は高くなります。
- 資金使途と返済計画がわかる資金繰り表を銀行に提示している
- 収益性・将来性がわかる事業計画書を銀行に提出している
- コストの見直しなどで実は黒字にできるなど改善要素がある
- 税理士・公認会計士を通して銀行に紹介してもらっている
- 財務情報を定期的に銀行に提示している
- 銀行の担当者と良好な関係を築いている
- 経営者の人柄への信用が高い
- 経営者の経験・スキルが高い
- 調達先の銀行に資金の動きが活発な口座を開設している
*参照元:SalesZine
どうです? どれか当てはまりましたか?
どれも当てはまらない人は、銀行から融資を受けるにはハードルが高いです。
でも、あきらめないでください。
今から、事業計画書(資金繰り表を含む)を作成しても間に合います。
融資を受けやすくする裏技や、事業計画書、資金繰り表、財務諸表を作成する方法を、税理士や会計ソフトの両面から説明します。
将来の資金予測ができることで倒産を予防し、回避することができます。
融資を受けやすくする裏技
銀行の決算1ヵ月前に申し込む
一般の企業が決算を気にするように、銀行などの金融機関も株主や金融庁の目が気になるので決算を気にします。
そのため、決算の見栄えを良くするために融資実績を増やそうと、決算前になると赤字の会社も借りやすくなります。
プロパー融資を受けておく
赤字の決算の時には難しいかわかりませんが、それでも会社の業績が良い時に少額でも、どこの銀行でもいいからプロパー融資を受けていれば、赤字の時でも融資が受けやすくなります。
プロパー融資を受けていると信用度が上がり、他の銀行から
「あの銀行がプロパーで貸しているなら、この会社に貸しても大丈夫だろう」
と判断される可能性が高くなり融資も受けやすくなります。
短期借入こそ実質「無期限」の長期借入
銀行からの融資はできるだけ返済期間が長い方が、1回あたりの元金返済も少なく長く借りられるので良さそうですが、
実は短期借り入れの方が、長期的に資金繰りを良くする実質「無期限」の長期借入金なのです。
融資を申し出る際にも長期借入金よりも短期借入金の方が審査が通りやすいです。
1年後に一括返済する条件の短期借入金は、借入期間中の元金返済がなく、利息を払うだけです。
毎回の返済に元金を含める必要がないので、借入した資金はほとんど減ることがありません。
短期借入金は利息をきちんと支払っていれば、借り手が希望すれば借入契約を延長してくれます。
返済期限が近づくと銀行から延長の申し出があるので「はい、延長でお願いします」と答えるだけで、借入期間を1年延長することができます。
翌年も同様の流れが繰り返され、利息を払っている限り短期借入金は無期限の借入金になるのです。
この手法を短期継続融資といいますが、金融庁も推奨している融資です。
ぜひ活用してみてください。
銀行の本音
赤字でもこれを改善すれば融資を受けやすくなります。
銀行員が社長に言わない本音を暴露します。
まず、これを覚えておいてください。
銀行員はいくら親しくなったようでも「本音は言いません」というより言えないのです。
銀行員の言うことを真に受けていると、気づかないうちに融資が受けにくくなっていた。
ということがあるので注意してください。
次の3つの事項のうち、あなたが一つでもあてはまるのなら融資は難しいでしょう。
逆に改善すれば融資は受けやすくなります。
役員貸付金
役員貸付金は、銀行が忌み嫌うもののひとつです。
決算書に「役員貸付金」はNGです。
というのも銀行は決算書に「役員貸付金」が計上されているとこう考えます。
- 会社にお金を貸しても、社長個人のプライベートに使われてしまう かもしれない。
- 銀行から融資を受けるまえに、借りているお金を会社に返すべき。
ですので、融資を受ける前には決算書から「役員貸付金」を消してしまいましょう。
「役員貸付金」を消すには、社長の資産から返済するか、他から借りて返済をする方法があります。
借りたお金の返済は役員報酬を増額するなどの対応策をとることができます。
粉飾決算
粉飾決算が悪いことは百も承知しているから、絶対にしていない。と自信があるかも知れませんが、
ひょっとしたら、こんなことはしていませんか?
- そもそも赤字なので税金はゼロ。これ以上、経費を増やしても税金が減るわけではないので、減価償却はしないでおく。
- これ以上赤字を増やさないために、買掛金や未払金の計上を見送る。
税務署はこれで良くても、銀行はこれらは粉飾決算ととらえます。
銀行員はこれらの内容はわかっていても、「粉飾決算です」と問い詰めたりしません。
仮に社長から先に銀行員に話していても「その分利益から差し引いて見ているので大丈夫ですよ」としかいいません。
しかし、内情は粉飾があれば「もっとあるかも?」と見られているのです。
銀行から誤解される自覚なき粉飾決算
前述の減価償却、買掛金、未払い金の未計上以外にも、経営者が自覚がないままに、銀行から粉飾と誤解される決算を行っている場合があります。
貸付金・前払費用などを流動資産にする
1年以内に現金化される、あるいは費用化される資産は「流動資産」、1年を超える資産は「固定資産」に分類する。というルールがあります。
これをなんとなくで「流動資産」に分類してしまうと、会社の安全性指標である「流動比率(流動資産÷流動負債)」を実際よりもよく見せることになり、銀行から粉飾を疑われます。
特別利益を営業外収益にする
本来は特別利益として計上すべき、固定資産や有価証券の売却利益、生命保険解約による利益を特別利益ではなく営業外収益に計上することで、
実際よりも「経常利益を大きく見せる」ことになり、利益を偽っているという点で粉飾が疑われ銀行の誤解を招きます。
貸倒引当金を計上しない
売掛金や受取手形、貸付金などの「債権」があれば、回収不能の可能性を見込んで貸倒引当金を計上します。
経費となるので節税にもなり税法で上限が決められています。
銀行は、上限額までの貸倒引当金を計上していない、あるいは、まったく計上していないような決算書は粉飾と見なします。
銀行はどんな些細なことでも、なにかひとつ見つかれば、「他にももっとあるんじゃないか?」と疑いを持ちます。
税務署には問題ない決算書でも、銀行では粉飾と見なすケースがあるので注意が必要です。
税務署は架空売り上げを計上したリ、仕入金額を過小計上したりして、利益を増やす行為は、まったく問題にしません。
税金を増やす行為だからです。
しかし、銀行の見方は全く違うということを覚えておいてください。
中小企業の事業主の方は、税務署が問題ないのなら銀行も同じで問題がないと考えがちですが、そうではないことを肝に銘じる必要があります。
社長の個人資産を開示しない
銀行は担保に取るつもりはなくても、個人資産の存在を確認します。
いざというときには、それらが返済原資になるからです。
銀行員が社長に言わない「融資条件」に、社長の個人資産。社長個人名義の預金や不動産などがあります。
個人資産の存在を確認さえできればいいということもあるので、個人資産について、情報開示を拒否するのは融資を受けるにあたっては得策とは言えません。
銀行が融資したくなる企業
- 決算書の数字が安定している
- 融資が複数の銀行に分散している
- 資金使途と返済原資がはっきりしている
(何に使うお金でどうやって返すお金なのかがはっきりしている) - 経営者の人格(かなり重要)
- 短期融資を希望する企業
(「賞与資金」や「納税資金」は、返済期間の短い融資として、銀行のひもが緩くなる傾向にあります。)
税理士にお願いする

あなたは税理士と顧問契約を結んでいますか?
顧問税理士がいるのなら、事業計画書を作成してもらいましょう。
ただ、税理士でも得意不得意があって、決算書作成は得意だけれど、事業計画書作成、経営アドバイスはさっぱりという税理士もいるんです。
というよりも、そういう税理士が多いんです。
というのも、税理士の試験には決算に関する勉強はあるのですが、中小企業診断士や、経営管理士などの勉強科目はありません。
ですので、経営アドバイスをするのなら経理士自身が税理士以外の別の資格を取得するか勉強している必要があります。
もし、あなたの税理士が決算だけの勉強をした税理士なら事業計画書、資金繰り表の作成は無理かもしれません。
そうであれば自分で、事業計画書を作成するか、事業計画書作成が得意な税理士に変更することです。
税理士の変更なら、税理士紹介サイトで、事業計画書、資金繰りの作成が得意という条件を出せばすぐに見つかりますよ。
良い税理士が見つかれば、こんなアドバイスがもらえますよ
- 自社に適した資金調達先の選び方
- 自社に適した借り方(金額・金利・返済方法)
- 融資が受けやすくなる方法
- 事業計画の作り方
- 銀行との付き合い方
- 返済が難しくなった場合の対処方法
- 銀行の評価を高める方法
- 銀行の評価方法(格付け)と自社の評価
- 財務諸表の見方
- 返済計画の作り方
- 固定資産の償却
- 金融機関の紹介
*参照元:SalesZine
資金繰りが緊急を要するのなら、まず税理士に借入できそうな金融機関を紹介してもらいましょう。
そして、税理士と一緒に早急に経営計画書を作り上げるのです。
今の税理士が頼りないのなら、税理士を変更するしかありません。
会社が倒産するか、税理士を変更するか決断する時が来ています。
【関連記事】
税理士紹介サイトはたくさんありますが、おすすめは業界最大手の「税理士ドットコム」です。
税理士登録数、税理士紹介実績が業界最多で、完全無料で利用することができます。
税理士紹介サービス業界内で唯一の上場企業が運営していることも安心、信頼の材料です。
問合せの相談内容欄に、
「融資先の銀行を紹介してくれ、経営計画書を作成してくれる税理士を紹介してください。」
と書き込みましょう。
早ければ、その日のうちに適切な税理士を紹介してもらえますよ。
【関連記事】 税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
税理士ドットコム以外の税理士紹介サイトはたくさんあります。
税理士紹介サービス20社をランキング形式で評判を比較しています。
> 税理士紹介サイトどこが良いか、おすすめを独断と偏見でランキング
経営が悪化する中小企業の特徴
気が付いた時には、手遅れだったということがないように、次の事項に一つでも当てはまるのなら、早めに手を打っておく必要があります。
- 資金繰り状況を把握していない
- 売上・支出の増加・減少の見立てができていない
- 短期(月次・年次)事業計画を立てていない
- 財務諸表の見方がわからない
- 借入金の返済計画に無理がある
- 売掛金の回収と支払いのバランスが悪い
- 中長期(3年以上)事業計画を立てていない
- 人件費をかけすぎている
- 損益計画に無理がある
- 投資計画に無理がある
- 毎月の記帳作業が後回しで業績の把握が遅い
- 銀行と上手く付き合っていない
- 経費を掛け過ぎている
- 市場環境の変化に会社がついていけない
*参照元:SalesZine
自分で事業計画書、資金繰り表を作成

いや、それよりもこの際、経費節約で自分で事業計画書、資金繰り表を作成するということであれば、会計ソフトを使用することで、時間もかけることもなく簡単に作成できますよ。
というのも、今の会計ソフトはそれだけ優秀ということなんです。
会計ソフトも、数多くありますがおすすめは業界最大手の「マネーフォワード」です。
銀行口座やクレジットカード・電子マネー・POSレジ・通販サイトなどの金融関連サービス数は国内No1の3,600以上
取引明細を自動取得するので、日付・金額・摘要・勘定科目の単純な打ち間違いなどによるミスが無くなり、大幅な時間短縮ができます。
紙の領収書や、レシートも自動で読み取り・データ化してくれます。
初期費用が0円から使用でき、自動集計した結果をリアルタイムに経営資料に反映させることができます。
「マネーフォワード」のキャッシュフロー計算書と、予定実現機能を使うことで資金繰り表に活用することができます。
銀行に提出する財務諸表も瞬時に作成可能です。
社労士や税理士も使っている優れものの会計ソフトです。
初心者向け導入サポートもあるので、メール、チャットなどで相談することができます。
今なら、質問に答えるだけで、次のことがわかるサービスもあります。
![]()