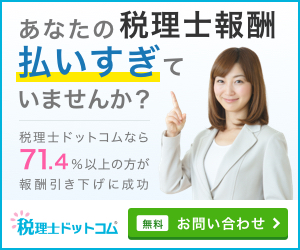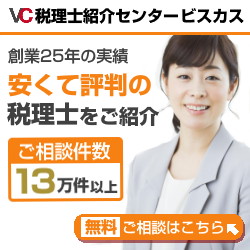本ページはプロモーションが含まれています。
確定申告 税理士 丸投げ 費用!確定申告 丸投げ パックは安い?

この記事では、確定申告 税理士 丸投げ 費用や、確定申告 丸投げ パックは安い?などを詳しく紹介しています。
料金的には、どの業態にも言えることですが、確定申告 丸投げパックは安いです。
しかし、丸投げといっても、依頼する業務はたくさんあります。
全体の料金だけでなく、税理士に丸投げする業務をひとつずつ業務内容別に細かく分けて料金も紹介しているので、
税理士に丸投げを依頼するときに提示される見積り料金と比較してみてください。
確定申告 丸投げには、時間や手間を節約でき、税務上のミスやトラブルを防げるメリットもありますが、デメリットもあります。
それらも詳しく紹介しています。
それよりも、すぐにでも確定申告 丸投げ パックを取り扱っている税理士を探したいという方はこちらをご覧ください。
確定申告 丸投げ パックは安い
近年、「確定申告丸投げパック」というプランを用意している税理士事務所が増えています。
「確定申告丸投げパック」は、文字通り確定申告を税理士に丸投げできるサービスです。
通帳や一年分の請求書・領収書(レシートなど)等を税理士に渡すと、税理士が通帳や領収書を区分けして帳簿・決算書・確定申告書を作成してくれます。
作成された確定申告書をもとに、所得税を納める(又は還付を受ける)ことにより確定申告は終了します。
料金はパックというだけに、記帳代行を含め通常よりもお値打ちな料金が設定されています。
また、安いだけでなく、確定申告完了まで最短「1日」と、スピードを謳うところもあります。
確定申告丸投げパックのほとんどが月額顧問料が不要で、確定申告のみの対応で、
年商1,500万円以下とか、従業員無しの個人事業主、フリーランスなどを対象にしている事務所が多いです。
ただし、従業員を雇用している場合の年末調整、仕訳数が100仕訳超える、消費税の申告、インボイス制度対応、節税相談などはオプション扱いになるので、実際の金額は状況により異なります。
あとあと、トラブルにならないためにも、初めに契約内容やサービス範囲を確認しておく必要があります。
税理士丸投げ費用、確定申告の相場

税理士丸投げ費用、確定申告の相場を、フリーランス、個人事業主、法人の順に紹介します。
確定申告 丸投げ フリーランス
白色申告
売上が少ない個人事業主やフリーランスが対象になります。
約50,000円〜100,000円程度
白色申告は、少し勉強すれば自分で作成することもできるので、最終チェックだけを税理士に依頼するということであれば、料金はもっと安くすることができます。
個人事業主 税理士 丸投げ 費用
青色申告
個人事業主(事業所得)の青色申告は、「売上規模」「記帳代行(会計ソフトへの入力業務)の有無」。
この2点によって費用が変動します。
|
年間売上高 |
自分で記帳する場合 |
記帳代行も依頼する場合 |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 5万円〜 | 10万円〜 |
| 500万円〜1,000万円未満 | 7万円〜 | 15万円〜 |
| 1000〜3000万円 | 10万円〜 | 20万円〜 |
| 3000万円〜5000万円 | 15万円〜 | 25万円〜 |
| 5000万円以上 |
要相談 |
|
税理士 丸投げ費用 法人
青色申告と比べると、売上規模は同じでも税務処理が複雑になるために高くなります。
|
年間売上高 |
自社で記帳する場合 |
記帳代行も依頼する場合 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 15万円〜 | 20万円〜 |
| 1000〜3000万円 | 20万円〜 | 25万円〜 |
| 3000〜5000万円 | 25万円〜 | 30万円〜 |
| 5000〜7000万円 | 30万円〜 | 35万円〜 |
| 7000〜1億円 | 35万円〜 | 40万円〜 |
| 1億円〜 |
要相談(50万円以上) |
|
税理士に丸投げする費用は売上基準
基本的には1年間の売上を基準にして年間の税理士費用を決めている税理士が多いです。
年間売り上げの5〜8%
<<業務内容>>
記帳代行(領収書等の資料の整理も含む)、決算書・申告書の作成、定期的な会社訪問、随時税務の相談
年間売り上げの3〜6%
<<業務内容>>
決算書・申告書の作成、定期的な会社訪問、随時税務の相談
*資料整理、会計記帳などは自社で行う
税理士 丸投げ 費用 業務内容別
次の表は、丸投げ費用を業務内容別により細分化したものです。
税理士への報酬は業務内容ごとに料金設定がされていて、税務調査の立会い・融資相談・節税対策・経営計画の策定などはオプションメニューとして別途費用が設定されている事務所が多いです。
税理士と丸投げの契約を結ぶ前に、見積りを出してもらい確認、納得をしてから依頼するようにしましょう。
そうすることで、契約後に依頼した業務内容が料金内に含まれている・いないで揉めるトラブルを防ぐことができます。
ここから必要な依頼内容を合計することで、だいたいの目安がつくと思います。
年間売上高には準じていないので、あくまで参考資料になります。
初回のみの費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 会計ソフト導入と保守、自計化サポート | 50,000円 |
毎月の費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行(100仕訳あたり) | 10,000円 |
| 会計処理の説明 | 10,000円 |
| 会計帳簿のチェック、処理の訂正 | 10,000円 |
| 月次状況報告 | 10,000円 |
| 毎月の資金繰りの相談 | 10,000円 |
| 資金繰り表の作成 | 30,000円 |
| 元帳および試算表の作成 | 30,000円 |
| 給与計算(1名につき) | 1,000円 |
| 月次事業報告書作成 | 50,000円 |
| 金融機関同行(1行につき) | 10,000円 |
| 経営コンサルティング | 50,000円 |
年1回の費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 決算処理(法人税・事業税・住民税・消費税の税務書類作成、税務申告含む) | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| 年末調整と法定調書、給与支払報告書の作成(1名につき) | 5,000円 |
| 償却資産税申告書の作成(1市町村につき) | 50,000円 |
| 事業所税申告書の作成(1市町村につき) | 50,000円 |
随時・依頼時の費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 融資に関する資料作成(A4・1枚当たり) | 30,000円 |
| 融資による資金調達サポート | 調達額の5% |
| 事業計画書作成 | 300,000円 |
| 税務調査立ち会い(1日当り) | 50,000円 |
| 株主総会議事録作成 | 50,000円 |
| 専門家紹介(社会保険労務士・司法書士・行政書士・中小企業診断士等) | 30,000円 |
| スポット相談(1時間) | 30,000円 |
丸投げ業務項目には、これらなどがあげられますが、
予算の関係で丸投げができないという場合は、相談をして部分的に必要な代行も対応可能です。
税理士に丸投げするデメリット
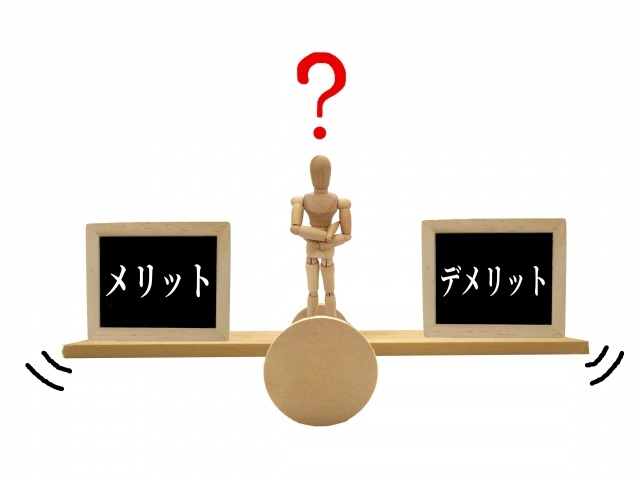
費用がかかる
領収書の整理や仕訳は思いのほか時間がかり、仕訳数が増えるほど税理士費用は高くなります。
しかし、費用が高すぎる場合は節約する方法もあります。例えば、
複数の税理士から見積もりを取って比較したり、
自分で簡単な記帳や整理を行ってから税理士に依頼する
などです。
自分で経理を把握しづらくなる
税理士に丸投げすることで、数字が把握できないまま、業務を進めていくことになります。
経営に不可欠な日々の経費の数字が把握できにくいです。
税理士が記帳することで、リアルタイムに情報をフィードバックしてもらえば、カバーできると思われますが、税理士から月次の試算表としてフィードバックされるのは、2〜3ヶ月後になります。
資料を税理士に渡すのが、決算前の1回だけで1年分だとしたら、1年間は全く会社の業績の数字が見えないことになります。
税務知識が身に付かない
自社で経理することで、税務知識が身についていきますが、税理士に丸投げすることで税の知識が身につかずに節税対策も上手くすすめられない場合があります。
信頼できる税理士を見つける必要がある
税理士に丸投げすることで、自分の事業に関わる重要な情報や責任を委ねることになります。
そのため、信頼できる税理士を見つけることは非常に大切です。
税理士に丸投げするメリット
時間や手間を節約できる
会計業務や確定申告は、個人事業主にとって必要不可欠な作業ですが、非常に時間や手間がかかるものです。
例えば、確定申告では以下のような作業が必要です。
- 収入・支出・資産・負債などの帳簿作成
- 青色申告決算書・損益計算書・貸借対照表などの書類作成
- 税金額の計算
- e-Tax等での提出
これらの作業は一般的に数日から数週間程度かかるものです。
また、記帳代行では以下のような作業が必要です。
- 領収書・請求書・契約書等の整理
- 売上・経費等の入力
- 消費税等の計算
- 印鑑証明等の取得
これらの作業は一般的に月数時間から数十時間程度かかるものです。
これらの会計業務を自分で行う場合は、多くの時間や手間を費やすことになりますが、税理士に丸投げすることで、これらの作業を全て任せることができます。
また、税理士は最新の税制や法律にも精通しているので、適切な申告や節税対策を提案してくれます。
税務上のミスやトラブルを防げる
会計業務や確定申告は、自分で行う場合には様々なミスやトラブルが発生する可能性があります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 帳簿作成や書類作成に誤りがある
- 税金額の計算に間違いがある
- 申告期限を過ぎてしまう
- 税務署から追徴課税や課税証明書等の通知が来る
これらのミスやトラブルは、自分で対処する場合には大きな負担となります。
帳簿作成や書類作成に誤りがある場合は、訂正申告を行わなければなりません。
税金額の計算に間違いがある場合は、多く納めすぎた場合は不利益を被ります。
申告期限を過ぎてしまう場合は、延滞税や罰則が科されます。
税務署から追徴課税や課税証明書等の通知が来る場合は、追加で納付したり、証明書を提出したりしなければなりません。
これらのミスやトラブルを防ぐためには、会計業務や確定申告を正しく行うことが必要ですが、それには専門的な知識や経験が必要です。
しかし、個人事業主であれば、会計業務や確定申告に関する知識や経験は十分ではないかもしれません。
また、自分で行う場合には人間的なミスも起こり得ます。
そこで、税理士に丸投げすることで、これらのミスやトラブルを防ぐことができます。
税理士は会計業務や確定申告に関する専門知識や経験を持っているだけでなく、常に最新の情報をキャッチアップしています。
また、税理士は個人事業主の事情に応じて最適なアドバイスをしてくれます。
さらに、万一ミスやトラブルが発生した場合でも、代表して対応してくれます。
税理士に丸投げすることで得られる安心感や信頼性は大きいです。
自分では不安だったり困ったりするような問題もプロに任せることで解決できます。
節税対策や経営相談が受けられる
会計業務や確定申告を自分で行う場合には、節税対策や経営相談を受けることが難しいかもしれません。
しかし、税理士に丸投げすることで、節税対策や経営相談が受けられるメリットがあります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 節税対策の例とその効果
- 青色申告特別控除や小規模企業共済等の制度を活用する
- 経費の適切な区分や計上方法を知る
- 資産の有効活用や減価償却等の方法を知る
- 法人化や合同会社設立等の選択肢を検討する
これらの節税対策は、自分では知らなかったり忘れていたりするようなものも多いかもしれません。
しかし、税理士はこれらの節税対策に精通しており、個人事業主の状況に応じて最適な提案をしてくれます。
これにより、納めるべき税金額を最小限に抑えることができます。
◆経営相談の例とそのメリット
- 売上・利益・キャッシュフロー等の数字分析や予測を行う
- 経営計画や目標設定等の支援を行う
- マーケティングや販促等の戦略立案や実行支援を行う
- 資金調達や資金繰り等のアドバイスを行う
税理士に丸投げする際の注意点と流れ

税理士に丸投げする際には、契約内容やサービス範囲を確認しておくことが重要です。
また、依頼前から契約後までの流れを把握しておくことも大切です。
注意点
契約内容やサービス範囲を確認しておく
税理士に丸投げする場合、契約内容やサービス範囲は必ず書面で明確化しておきましょう。
口頭での約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。
契約内容やサービス範囲には、以下のような項目が含まれることが多いです。
- 依頼する業務の種類や期間(記帳代行、決算申告、税務相談など)
- 報酬の金額や支払い方法(月額制、年額制、成果報酬制など)
- 業務委託時の連絡方法や報告方法(電話、メール、オンラインミーティングなど)
- 業務委託時の責任分担や損害賠償の有無(過失責任、保険加入など)
- 契約期間や更新条件(自動更新か否か、解約条件など)
これらの項目を事前に確認しておくことで、税理士との信頼関係を築くことができます。
チェックリスト
|
項目 |
条件 |
チェック |
|---|---|---|
| 依頼する業務 | 記帳代行・決算申告・税務相談・その他 | |
| 報酬金額 | 月額〇万円・年額〇〇万円・成果報酬〇〇%・その他 | |
| 支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード・その他 | |
| 連絡方法 | 電話・メール・オンラインミーティング・その他 | |
| 報告方法 | 毎月月末・毎四半期末日・年度末日・その他 | |
| 契約期間 | 1年間・自動更新あり・解約通知3か月前まで | |
このチェックリストを税理士と共有して、契約内容やサービス範囲について合意しておきましょう。
もし、不明点や不満点があれば、税理士に質問したり、交渉したりしてください。
よくあるトラブルや解決方法
税理士に丸投げする際には、契約内容やサービス範囲に関するトラブルが起こることがあります。
以下は、よくあるトラブルの例と解決方法です。
- トラブル例:税理士が依頼した業務以外のサービスを提供して、追加料金を請求する。
- 解決方法:契約書に依頼した業務の範囲を明記しておく。追加料金は事前に相談して合意する。
- トラブル例:税理士が業務委託時の連絡や報告を怠る。
- 解決方法:契約書に連絡や報告の方法や頻度を明記しておく。連絡や報告がない場合は催促する。
- トラブル例:税理士が過失で会計ミスを起こし、税務罰則を受ける。
- 解決方法:契約書に過失責任の有無や損害賠償の条件を明記しておく。税理士が保険に加入しているか確認する。
これらのトラブルは、事前に契約内容やサービス範囲を確認しておけば防ぐことができます。
もし、トラブルが発生した場合は、税理士と話し合って解決しましょう。
話し合いで解決できない場合は、弁護士や消費者センターなどの第三者機関に相談しましょう。
確定申告 税理士に渡すもの
売上伝票や領収書など、税理士に提出する書類は分かりやすく整理しておきます。
生理されていない状態で書類を渡してしまうと、税理士は整理するところから始めないといけないため、余計な手間(経費)が掛かってしまいます。
税理士に書類を渡す際は最低限、
- 月ごとに分ける
- カテゴリーごとに分ける
- プライベートの領収書は取り除いておく
といったように整理しておくといいでしょう。
誤記入・記入漏れなどを防ぐためにも、書類は整理した状態で渡すことが重要です。
領収書
事業のために使った費用=「必要経費」を漏れなく正確に計上するために、支出を証明する領収書は確実に発行してもらい、保管しておきます。
経費にできるのかどうか判断に迷うような場合にも取っておいて、税理士の判断を仰ぎます。
領収書を税理士に渡すとき、「事業にどう関わっているのか」を説明します。
説明が無いと税理士は正確な記帳が難しくなってしまいます。
請求書
受け取った請求書も、領収書と同様に取引の証拠となる大切な文書です。
支払い後も保存し、税理士に渡します。
預貯金の通帳やネットバンキングの取引記録
コピーでいいのでコピーして税理士に渡します。
できれば、事業専用の口座を開設し、管理するとわかりやすいです。
これらの文書は、「すべてが揃ってからまとめて」ではなく、毎月あるいは四半期ごとに提出を求められます。
支払調書
報酬を支払った先から発行される文書で、1年間の報酬額のほか、源泉徴収額、消費税額などが記載されています。
これは法定調書(税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類)と呼ばれますが、確定申告書に添付する必要はありません。
控除に関する書類
例えば生命保険の保険料は、所得から差し引く(控除する)ことができます。
他にも、住宅ローン控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除などがあります。
これらに該当する控除があれば、税理士に申し出ます。
税理士報酬を少しでも下げるには
税理士・会計事務所から見積りを取り比較をすることで、必ず個人事業主が税理士に丸投げする費用は安くなります。
次の手順で比較をしてみてください。
ネットで1社1社調べるよりも、正確な金額が確認できて手間もかかりません。
- 税理士に依頼する内容をまとめる
- 問合せをする税理士・会計事務所を数か所選ぶ
- 各事務所に依頼内容を伝える
- 各事務所の費用を提示してもらう
- 一番安いところを選ぶ
税理士・会計事務所選びには、税理士紹介サービスを利用します。
税理士報酬の削減に力を入れている税理士紹介サービスを選んで探すのがおすすめです。
税理士に依頼する項目は、詳しいほどあとあとトラブルになることを避けることができます。
丸投げできる税理士を探す方法

丸投げ可能な税理士事務所の選び方について、以下の4つのポイントを解説します。
料金
料金は、依頼する業務の内容や範囲、税理士事務所の規模や地域などによって変わります。
料金を比較する際は、契約期間やキャンセル料なども確認しましょう。
サービス内容 サービス内容は、税理士事務所によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
- 確定申告書作成・提出代行
- 経理処理(伝票整理・帳簿作成・決算書作成)
- 税金計算・納付代行
- 税務相談・アドバイス
- 補助金・助成金申請代行
- 法人設立・廃業手続き代行
サービス内容を比較する際は、自分が必要とする業務や範囲を明確にしましょう。
また、オンラインで対応してくれるかどうかも重要です。
評判
評判は、インターネット上で口コミやレビューを見ることができます。
評判を比較する際は、以下のような点に注意しましょう。
- 対応速度や連絡方法
- 専門性や信頼性
- コミュニケーション能力や親身さ
- トラブル対応やアフターサポート
評判だけではなく、実際に相談してみることも大切です。
対応地域
対応地域は、自分が住んでいる地域や事業所がある地域と同じか近いかどうかです。
対応地域を比較する際は以下のような点に注意しましょう。
- 移動時間や交通費
- 地元情報やネットワーク
- 面会頻度や打ち合わせ方法
オンラインで対応してくれる場合でも、面会や打ち合わせが必要な場合があります。
オンラインでの対応に慣れているかどうかも重要です。
信頼できる税理士の条件や特徴
- 自分の事業内容や規模に合ったサービスや料金体系を提供している
- 自分のニーズや疑問に対して丁寧かつ迅速に回答してくれる
- 自分の事業成長や節税対策などに積極的かつ具体的にアドバイスしてくれる
などが挙げられます。
信頼できない税理士の特徴
信頼できない税理士は以下のような特徴があります。
- 費用が不透明だったり、相場よりも高すぎたり安すぎたりする
- コミュニケーションが不十分だったり、無視したりする
- 違法な節税方法やリスクの高い手法を勧めてくる
このような税理士は避けるべきです。
コスト削減に強い税理士紹介サービス

コスト削減に強い税理士を探すのには、以下のような方法があります。
- SNSで口コミや評判を参考にする
- インターネットや電話帳で検索する
- 知人や友人に紹介してもらう
- 税理士紹介サイトやマッチングサイトを利用する
- 「日本税理士会連合会」から探す
しかし、一人ひとり検索して確認し、問い合わせをすることは大変です。
おすすめは税理士紹介サービスを利用する方法です。
ここでは、おすすめの税理士紹介サービスを4つ紹介します。
どの税理士紹介サイトも、税理士を変更したことで税理士報酬が下がったという実績をアピールしています。
税理士ドットコム
なんといっても税理士紹介サービスでおすすめなのは「税理士ドットコム」です。
「税理士ドットコム」は登録税理士数、紹介案件数が業界最大手で、業界で唯一上場会社の運営です。
税理士ドットコム以外の税理士紹介サービスは登録税理士の情報が公表されていませんが、税理士ドットコムなら、ホームページから地域別に登録税理士全員を確認することができます。
利用料は無料で、希望する条件をメールで送るだけで、あなたの条件にあった税理士を希望すれば何人でも紹介してもらえます。
税理士と面談して、あなたの希望とマッチしない時は税理士ドットコムが断ってくれるので、あなたが負担に感じることはありません。
税理士ドットコムを利用した方の71.4%が税理士報酬を下げることができています。
プロのコーディネーターが要望にあった税理士を探してくれます。
最短当日|24時間受付|年中無休|全国対応
【関連記事】 税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
税理士紹介センタービスカス
税理士紹介センタービスカスは税理士紹介サービスを日本で最初に始めたパイオニアです。
創業が1995年と古く、運営年数は業界最多です。
税理士紹介センター ビスカスは、税理士を紹介したらそれで終わりではありません。
利用した方の5年後のアンケート調査では、86%の方が満足と答えています。
顧問料見直し事例もホームページに公表されています。
↓メール24時間受付中↓
【関連記事】 税理士紹介センタービスカス 評判、迷惑電話、SNSの口コミを紹介
税理士紹介ラボ
税理士紹介ラボは、ホームページでも訴求しているように、コスト削減にこだわった税理士を紹介しています。
ただし、安いからといって税理士のサービスがおろそかになることがないように税理士紹介ラボが責任を持って対応しています。
税理士紹介ラボは、他にも
- 無料保険相談の保険ラボ
- 火災保険の一括見積もりサービス「火災保険KURABEL」
- 不動産紹介サービス「不動産紹介ラボ」
も運営していて、他社と比較して費用を見直すサービスには、かなりのノウハウ、営業力があります。
税理士費用の削減を考えているのなら、税理士紹介ラボはおすすめ税理士紹介サービスの一つです。
↓税理士顧問契約で1万円プレゼント↓
【関連記事】 税理士紹介ラボの評判、口コミ!税理士報酬を削減するならおすすめ
ベンチャーライフ
決算料0円の丸投げ税理士紹介サービス
ここで紹介される税理士は全員が決算料0円で、売上に応じて報酬が決まっています。
費用交渉をする必要もないので、あとは税理士との相性を確認するだけです。
丸投げ業務の内容
| ・来所又は訪問での相談 ・電話・メールでの相談 ・税務代理権限証書作成 ・適時月次試算表の作成 ・決算報告書の作成 ・内訳・概況書の作成 |
・消費税申告書の作成 ・法人税申告書の作成 ・申告書提出の代行 ・総勘定元帳の作成 ・税金納付書の作成 ・税務届け出書の作成 |
これだけの業務が、下記の料金内できっちり対応してもらえます。
|
年間売上高 |
月々 |
決算料 |
年間 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 10,000円 |
0円 |
120,000円 |
| 3,000万円 | 15,000円 |
0円 |
180,000円 |
| 5,000万円 | 220,000円 |
0円 |
240,000円 |
| 1億円 | 30,000円 |
0円 |
360,000円 |
| 1億円超 | 応相談 |
0円 |
応相談 |
こちらから、あなたの会社の近くの決算料0円の税理士を紹介してもらえます。
↓問い合わせはこちらから↓
【関連記事】 ベンチャーライフ 評判!税理士の顧問料 月1万円〜。決算料0円
4社以外の税理士紹介サービスもこちらで確認できます。
よければ比較してみて下さい。
>> 税理士紹介サイトどこが良いか、おすすめを独断と偏見でランキング
個人事業主 税理士 丸投げ 費用:Q&A
税理士に丸投げすると、以下のようなメリットがあります。
- 確定申告や税務調査に対応してもらえるので、税金の知識や手続きに悩む必要がなくなります。
- 会計や経理の業務を任せることで、自分の本業に集中できます。
- 税理士から経営や財務に関するアドバイスを受けることができます。
- 税金の節税や効率化を図ることができます。
税理士に丸投げする場合の費用相場は、以下のようになります。
- 白色申告であれば5〜10万円程度
- 青色申告であれば15万円〜
- 月次顧問料は10,000円〜
- 記帳代行料は1仕訳あたり50円〜
- 決算料は100,000円〜
ただし、これらはあくまでも目安であり、依頼する内容や規模、税理士事務所によって異なります。事前に見積もりを取って比較検討しましょう。
税理士事務所を選ぶ際のポイントは、以下のようなものがあります。
- 自分の業種や規模に対応しているかどうか
- オンラインで対応してくれるかどうか
- コミュニケーションがスムーズかどうか
- 費用やサービス内容が明確かどうか
以上のポイントを参考にして、自分に合った税理士事務所を探しましょう。
まとめ
個人事業主の税務に関する悩みは尽きませんよね。
確定申告や経理の処理、節税対策など、自分でやるのは大変です。
そこでおすすめなのが、税理士に丸投げする方法です。
これまでの説明で、税理士に丸投げする費用相場やメリット・デメリット、注意点や流れ、選び方が、ある程度理解できたのではないでしょうか?
税理士に丸投げする方法を知ったことで、税務の悩みから解放され自分の仕事に集中しましょう。