

本ページはプロモーションが含まれています。
税理士報酬が安いと思わせる手口にご用心!知っておくべきポイント
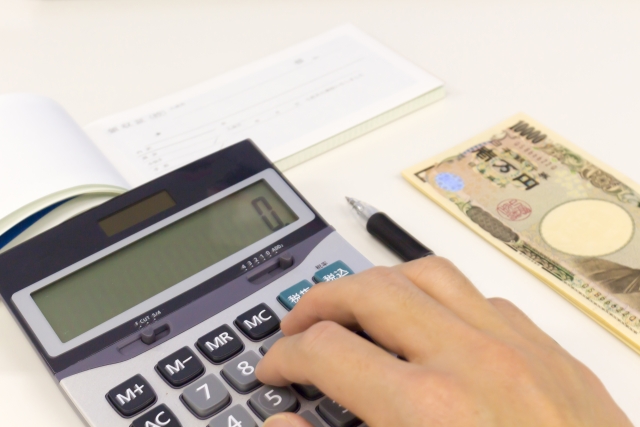
この記事では、税理士報酬が安いと思わせる手口を、具体的に紹介しています。
安さを標榜する税理士はたくさん存在します。
その多くの税理士は、安くしないと顧客を獲得できない知識やスキルが低い事務所がほとんどです。
もちろん、経営努力をして安さを実現している事務所もありますが、非常に稀です。
ここでは実例を交えながら分かりやすく、税理士報酬が安いと思わせる手口、格安税理士のデメリット、メリット、失敗事例を紹介しています。
税理士報酬一覧表も掲載しているので、税理士を選ぶ時の参考にしてみてください。
ごまかすことがない誠実な税理士を探すのなら、信頼できる税理士紹介サイトから紹介してもらうのが一番です。
【税理士紹介サイト ランキング!評判でおすすめの上位7社】
税理士報酬が安いと思わせる手口
ホームページで安く見せる
税理士報酬が安い格安税理士事務所のホームページでは、ほとんどが「顧問料〇千円〜」と書かれています。
実はこの「〜」は曲者なのです。
初めにアッと思わせる安い料金を掲載して注目を集めているのです。
それではと、その税理士事務所に問い合せて見ると、
「お会いしてみないと何とも言えませんが、えーこの料金は顧問しているという関係だけで、実際には何もしません。
これにデータチェックが加わると、プラス月5千円。月次訪問で1万円。決算料が10万円。確定申告8万円。年末調整がおひとり...、で、年間〇〇万円です。」
と答えが返ってくる事務所もあります。
嘘のような話ですが、本当の話です。
税理士が決算申告書にハンコを押して税務署に提出するということは、税務署からの問い合わせにも答えなければならないし、訴えられるかもしれないというリスクも負うことになります。
ですので税理士の顧問先は、普通安いところでも年間20〜30万円の料金をいただかないと割に合わないという事になります。
帳尻が合うように仕事をする
「個人事業主 税理士 安い」「税理士報酬 安い」「税理士報酬 安い」など、ネット上で検索すれば、顧問料を安い値段で引き受ける会計事務所や税理士事務所がいくらでもでてきます。
コストを抑えたいという気持ちは良くわかるのですが、よく考えて下さい。
あなたも経営者であれば税理士も経営者なのです。
あなたが「安くして」と言われたらどうしますか?
帳尻が合うように、どこか力を抜いて仕事をしませんか?
これと同じです。
低料金で税理士顧問を引き受けても税理士の都合で業務の帳尻を合わせようとするのです。
税理士報酬が安いのは次のようなパターンが多いです。
とにかく仕事を取ってきて、会計のことなど何もわからないバイトやパートさんに適当な入力をさせて、とにかく件数をこなす税理士。
(税理士が記帳代行サービスに丸投げすることもあります。)
ただ、毎月きちんと会計ソフトで会計処理をして試算表まで出来上がっている個人事業主なら、申告書だけの作成なので料金はグッと安くなります。
税理士によっては、年間3万円〜5万円で引き受けるところもあるでしょう。
ただし、ここで会計処理した内容をチェックしたりする業務が加わると、料金は大きく変わってきます。
事業規模にもよりますが、年間10万円くらいはもらわないと割に合いません。
いたずらに安さを求めるのではなく、税理士報酬の相場を知っておくことで適切な交渉をすることができます。
税理士報酬が安い具体的な失敗事例

税金を多めに払うことになる
税理士報酬を安い格安で引き受けていても、安いからといって決算後に税務調査が入ったり、追徴課税が取られたりすると信用が落ちてしまいます。
それで、税理士は格安で引き受けていてもそんなことがないように、決算申告書をどれだけ調べられても、文句のつけようのない申告書に仕上げます。
聞こえはとてもいいですが、つまりは税金を少し多めに払っているんです。
税金を多めに払うことで、税務調査が入ったり、追徴課税が取られたリすることがないようにしているのです。
オプション料金が加算され高くなる
初めは安い税金表を提示されていても、オプションを積み上げることで結局は高くなります。
基本、税理士への費用は項目別(記帳代行・決算申告・顧問料など)に料金が設定されています。
税務調査の立会い・税務相談・融資相談などは、別途費用としてオプションメニューで設定されている事務所が多いです。
料金表はいかにも安く見えるように作られているのですが、オプションを積み上げることで結局は相場料金かそれ以上になることがあります。
契約してみたら、含まれると思っていたサービスがオプション扱いだったという事例もあります。
節税アドバイスが適切でない
仮にあなたの会社が税引前利益で100万円の利益が出ると想定します。
この場合、法人税率が25%です。
この25万円がもったいないと節税を考えます。
浪費型
決算前に消耗品や備品を100万円分購入する。
必要な物ならいいのですが、どうしても勢いにまかせていらないものまで購入してしまいがちです。
また、取得価額30万円以上の固定資産は全額その年の経費にならずに、法定の期間で分割して減価償却されます。
まともな税理士なら、25万円は税金として支払い、残りの75万円を内部保留で積み立てておくことを説明しますが、
税理士の顧問料が安いと、親身な相談にのることができないので、説明の手間を省くために浪費型の節税をすすめることになります。
万が一、会社に資金が必要になった時に銀行が融資してくれる金額は、【税引後利益+減価償却費】の5倍から10倍です。
もし、無駄に浪費をしてしまうと、万が一の時にも銀行からお金を借りられなくなってしまいます。
生命保険や倒産防止共済を活用
生命保険や倒産防止共済は控除金額が変更になったりしますが、現在の倒産防止共済で説明すると、
年間240万円までの掛金は経費として処理できます。
法人税率を25%と仮定すると、60万円節税することができます。
掛け金の最大金額800万円まで積み立てると、合計で約200万円が節税できます。
しかし、この倒産防止共済を解約した場合には、約200万円の税金がかけられます。
つまり、差引のメリットはプラスマイナス0なのです。
親身になってくれる税理士なら、解約する時に経費を立てるような事業計画を提案してくれますが、
税理士の顧問料が安いと、相談に時間をかけることができないので、事業計画を提案することはまずないと考えた方がいいでしょう。
税理士報酬の時給単価

税理士報酬が安いからといって、そこで働く税理士の時給単価も安いわけではありません。
税理士の時間給計算は、ほとんどどこも同じで、時給単価が5、000円を下回ることはありません。
つまり、顧問料が月額1万円なら、その顧問先には2時間以上使わないのです。
月額5万円の顧問料なら、月に10時間使うということです。
仮に、月に2時間しか使えないとしたら税理士に何ができると思います?
せいぜい、会計記帳で手一杯でしょう。
残念ですが、経営相談、経営状況の対面報告、将来シミュレーションなど対応することは無理です。
税理士報酬が安い税理士も経営者です。
皆、計算してやっているのです。
税理士が正しい税務処理、会計処理をしようと思ったら1人で見れる会社数は20社ぐらいが限界なんです。
もし、月額3万円で20社だと売上ベースで60万円にしかなりません。
人一人雇って月60万円では利益を出せるわけないですよね。
安い値段でも利益を出している税理士がいたら適当な仕事をしているんです。
間違いだらけの適当な決算書を作っているんです。
安いというのは基本そういうことです。
中には、ちゃんと効率化した仕組みを作って一人で50件以上の会社を見れる様にしている税理士事務所もあるみたいですが、怪しいもんです。
税理士業界は、価格で勝負する税理士と、高単価だけれど良い仕事をする税理士に2分化しています。
税理士報酬が安い税理士選びに失敗しないために
料金表をよくチェック
税理士報酬 安い選びで失敗しやすいのが、「値段」で選んでしまうことです。
とにかく安いからと飛びつく前に、安いのには何か理由があるはずだと、まずは疑ってかかりましょう。
税理士事務所のホームページを見れば、事務所によっては実際の料金がかなり詳細に記載されています。
料金を明示している事務所は、信頼できる評価ポイントです。
契約内容は、料金だけでなく、サービス内容や期間、解約に関するルールなども含まれます。
契約前にしっかりと内容を把握し、納得できるものであるかを確認することが大切です。
税理士のサービス内容は事務所によって異なります。
個人事業主にとって必要なサービスが提供されているかを確認することが重要です。
たとえば、確定申告のみならず、帳簿作成や節税アドバイスなども含まれているかどうかも確認しましょう。
口コミや評価を確認する
顧問料が安いからといって、サービスが十分に提供されているかは必ずしも保証されていません。
そこで、実際にその税理士事務所を利用した人たちの口コミや評価を確認することが大切です。
特に、同業者や同じ業種の人たちからの評価は参考になることが多いです。
相性が良いかどうか確認する
税理士との相性が悪いと、スムーズな業務遂行が困難になることがあります。
初回の面談などで、相手の人柄やコミュニケーション能力などを確認し、相性が良いかどうかを判断することも重要です。
安さだけにこだわらない
顧問料が安いということは、それだけで税理士事務所を選ぶのは危険です。
料金だけでなく、信頼性やサポート体制、法令や税制の最新情報を把握しているかどうかなども含め、総合的に判断することが大切です。
これらのポイントを踏まえ、安い顧問料で失敗しない税理士を選ぶことが大切です。
見積りを取る
税理士報酬を確認するのに確かな方法は見積りを取ることです。
依頼する業務内容、訪問回数を決めたうえで見積もりを出してもらいます。
こうすることで実際の料金を確認することができ、契約後に依頼した業務内容が料金内に含まれている・いない、で揉めることもありません。
電話で直接話す
今はインターネットの「問い合わせフォーム」でやり取りすることができますが、直接話しをすることで人となりが伝わります。
税理士は外注先ではなく、ビジネスパートナーと考えて、相性が合うかどうかが大事です。
面談する

一番重要なのは税理士と面談することです。
遠方の場合は難しい場合もありますが、電話で話すよりも、よりつっこんで実際の業務の進め方や心配事なども伝えることができます。
税理士選びの一番重要なポイントは、繰返しになりますが、あなたと相性が合うかどうかです。
つまり、「話しやすいかどうか」ということです。
今は創業間もないので、1年間はお値打ちにして欲しい。とか値段のことも相談しやすいですよね。
このことを意識して税理士を決めるようにすればきっと失敗も無くなるでしょう。
そのためにも、複数の税理士と面談することをおすすめします。
格安税理士のデメリット
サービス内容が不十分
安い顧問料で提供されるサービスは、限られている場合があります。
そのため、必要なサポートを受けることができず、結果的にトラブルに発展する可能性があります。
経験不足の税理士を選んでしまう
顧問料が安いと、経験が浅い税理士を選ぶ傾向があります。
経験不足の税理士は、問題が発生した場合に適切なアドバイスをすることができず、トラブルにつながることがあります。
違法な手続きをされてしまう
税理士は、企業のために税務処理を行うため、権限があります。
しかし、経験の浅い税理士や、不正な行為をする税理士に依頼してしまうと、違法な手続きをされてしまう可能性があります。
違法な手続きをされてしまうと、企業にとって大きな問題になることがあります。
税務署からの指摘や調査で対応できない
安い顧問料で提供されるサービスによって、適切な書類の提出や税務処理が行われていない場合、税務署から指摘や調査を受けることがあります。
その際、税理士のサポートが必要になるのですが、安い顧問料で依頼した場合、必要なサポートを受けられず、結果的に問題が大きくなる可能性があります。
契約内容に落とし穴がある
安い顧問料で提供されるサービスには、契約内容に落とし穴がある場合があります。
例えば、初期費用は安く設定されているが、その後の追加料金が高額であったり、契約期間が長くなってしまうなどの問題が起こる可能性があります。
対応が遅い
安い顧問料で提供されるサービスは、人員不足であったり、忙しくなると対応が遅くなる場合があります。
急ぎの問題や緊急の相談に対応できない可能性があるため、企業にとっては不都合な場合があります。
以上が、「税理士報酬 安い」のデメリットです。
ただし、安い顧問料でも、信頼できる税理士事務所を選ぶことで、デメリットを回避することができます。
格安税理士のメリット
何といっても税理士報酬が安いことが一番のメリットです。
相場よりもはるかに安い料金で税理士に依頼することができれば、経費削減につながります。
また、顧問契約を結ぶのではなく、決算書の作成のみ依頼するなど、
さまざまなサービスメニューの中から、必要最小限のサービスだけを選択することもできます。
税理士報酬が高いのを安い料金に変える方法
今、契約している税理士を変更するつもりはないけれど、
税理士報酬が高いなと感じている方。
これから安い税理士を探そう、もしくは変更しようとしている方は、次のやり方を実践してみてください。
7つの方法を紹介していますが、どれか一つでも実践することで、税理士報酬を必ず安くすることができます。
1.記帳業務を自社で済ませる
記帳が済んだ状態で税理士に依頼すれば、税理士の負担はかなり減るので、税理士報酬もそれだけ大きく削減することができます
税理士報酬を安くする記帳ツール
記帳などは、今は記帳ツールの優れものが開発されているので、それを使用することで大幅に税理士報酬を抑えられるはずです。
会計ソフトでデータを共有出来れば毎月の顧問料は必要ありません。

今ならお試しで1ヶ月〜1年無料で使うことができる「弥生会計」
![]() 、「マネーフォワード クラウド」
、「マネーフォワード クラウド」![]() があります。
があります。
税理士事務所もほとんどが会計ソフトを導入しているので、同じ会計ソフトを使用していれば簡単にデーターを共有することができます。
2.対面の打合せをしない
顧客側の事務所で打ち合わせをする場合、税理士に移動時間や交通費などがかかり、それが税理士の費用に反映されます。
対面の打ち合わせをやめ、必要なやりとりは電話、メール、ZOOMなどで行い、
書類のやり取りもメール、郵便を使えば、その分税理士報酬は削減できます。
3.自社のビジネスに合わせて、必要な業務だけを依頼する
毎月の顧問料が負担なら、確定申告だけを依頼したり、あとは特別な問題が生じたときにだけ対応してもらうようにすれば、税理士報酬は大幅に節約できます。
たとえば最も大きな心配としては、税務調査が入った時ですよね。
大丈夫です。日ごろ顧問税理士がいなくても、税務調査の時だけ依頼することができる税理士もいます。
「強制調査」でない「任意調査」なら、日程を調整することができるので、その間に税理士を探し、対策を練ることになります。
日程調整は、1週間から1ヶ月の先延ばしなら問題はありません。
税務署は必ず調査内容を事前通知することが決められているので、税理士とはその内容に沿った対処方法を相談したり、戦略を練ったりすることができます。
4.税理士に決算のみを依頼する
税理士に決算のみを依頼することで、税理士報酬を安くすることができます。
この場合は、自分で会計ソフトを使い、帳簿類を整備しておく必要があります。
また、自社で行った会計処理が正しいものとして決算処理するのと、
入力されたデーターに誤りがないか、税理士がチェックしてから決算処理するのとでは、費用が変わってきます。
【関連記事】 税理士に決算のみ格安に依頼!
5.税理士に丸投げ
記帳代行(領収書等の資料の整理も含む)、決算書・申告書の作成など、すべてを税理に丸投げする場合でも、
確定申告丸投げパックというプランを用意している税理士事務所もあります。
パックというだけに、お値打ちな料金が設定されています。
【関連記事】 個人事業主が税理士に丸投げする費用
6.オンライン 税理士
IT技術の発達によりオンライン専門の税理士事務所が増えてきています。
オンライン税理士の報酬は安いです。
顧問料、決算料は通常相場の半額。
安いからといって質が落ちることはありません。
ITを活用して業務を効率化し、クラウド会計の利用やペーパーレス化、チャットツールの利用などにより、低価格で質の高いサービスが提供されます。
面談もすべてオンラインで、電話と違って顔を見ながら対話できるので安心して相談することができます。
オンライン対応が基本なので、対象エリアが限定されず全国対応が可能です。
7.複数の税理士から見積もりを取り比較する
税理士報酬を安くする最も効果的な方法は複数の税理士から見積もりをとって、費用の比較をすることです。
あなたが希望する同じ条件で複数の税理士から料金の見積りを取り、一番安いところに決めればかなり税理士報酬を削減できます。
税理士と言えどもサービス業です。
あなたが取引業者に行っているように、見積りを取って条件の良いところを選ぶだけです。
ただ、ネット上から税理士のホームページを見てもよくわかりません。
料金表はどこもいかにも安く見えるように作られているからです。
しかし、契約してみたら、含まれると思っていたサービスがオプション扱いだったりして、オプションを積み上げることで結局は相場料金かそれ以上になることがあります。
では、どうすれば信頼できてお値打ちな税理士を見つけることができるかですが、
次の手順で探せば簡単に見つかります。
- 現在顧問税理士に依頼している内容をまとめる
(これから税理士を探す方は依頼したい内容をまとめます) - 問合せをする税理士・会計事務所を数か所選ぶ
(税理士紹介サービスを利用) - 各事務所に依頼内容を伝える
- 各事務所の税理士報酬を提示してもらう
- 一番安いところを選ぶ
これだけです。
ネットで1社1社調べるよりも、正確な金額が確認できて手間もかかりません。
現在は地域にとらわれることなく、インターネットや郵送で簡単に依頼できます。
東京や大阪、福岡など地域を限定する必要はありません。
問合せをする税理士・会計事務所は、税理士紹介サービスに選んでもらいます。
税理士報酬の削減に力を入れている税理士サービスがあるので、そこを利用するのがおすすめです。
税理士に依頼する項目は、詳しいほどあとあとトラブルになることを避けることができるので、
この記事で紹介している税理士に依頼する項目別費用を参考にしてみてください。
税理士報酬の相場も紹介しているので、税理士から費用見積もりが提示されたときに比べることもできます。
税理士報酬一覧表
税理士報酬 相場
*参照元:会計ソフトfreee
|
年商 |
月額顧問料 |
決算申告 |
記帳代行(月額) |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 15,000円 | 107,000円 | 7,000円 |
| 1,000〜3,000万円 | 19,000円 | 129,000円 | 8,000円 |
| 3,000〜5,000万円 | 23,000円 | 150,000円 | 11,000円 |
| 5,000万円〜1億円 | 29,000円 | 173,000円 | 14,000円 |
| 1億〜5億円 | 40,000円 | 210,000円 | 20,000円 |
| 5億〜10億円 | 50,000円 | 235,000円 | 26,000円 |
| 10億〜 |
要相談 |
要相談 |
要相談 |
会社の規模や依頼する範囲によって金額は異なりますが、一般的には「顧問料は月3万円くらい」が相場です。
経営全般の相談まで行う場合は、月額20万円を超える場合もあります。
月額5,000円〜1万円程度の税理士報酬の場合
会計ソフトなどに入力したものをチェックする程度で、自身で負担する部分が増えます。
契約料金が安い場合は、会社訪問が毎月必ずというのではなく、数カ月に一度ということになるかもしれません。
いずれにしろ、頻繁にコミュニケーションをとるのは難しいです。
対面での面談は難しいので、メールやオンラインの面談がメインになると思います。
月額5,000円だと、税理士が対応する時間をかなり削減しないと業務として成り立たないので、
ほとんど相談には乗ってもらえないでしょう。
しかし、金額が高いから必ずしも良いわけではないこともあります。
ただし、高いだけでサービスの内容が伴っていない場合もあるので注意が必要です。
税理士報酬相場:項目別
年間売上高には準じていないので、あくまで参考資料になります。
初回のみの費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 会計ソフト導入と保守、自計化サポート | 50,000円 |
毎月の費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行(100仕訳あたり) | 10,000円 |
| 会計処理の説明 | 10,000円 |
| 会計帳簿のチェック、処理の訂正 | 10,000円 |
| 月次状況報告 | 10,000円 |
| 毎月の資金繰りの相談 | 10,000円 |
| 資金繰り表の作成 | 30,000円 |
| 元帳および試算表の作成 | 30,000円 |
| 月次事業報告書作成 | 50,000円 |
| 金融機関同行(1行につき) | 10,000円 |
| 経営コンサルティング | 50,000円 |
年1回の費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 決算処理(法人税・事業税・住民税・消費税の税務書類作成、税務申告含む) | 月額顧問料の6ヶ月分 |
随時・依頼時の費用
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 融資に関する資料作成(A4・1枚当たり) | 30,000円 |
| 融資による資金調達サポート | 調達額の5% |
| 事業計画書作成 | 300,000円 |
| 税務調査立ち会い(1日当り) | 50,000円 |
| スポット相談(1時間) | 30,000円 |
税理士報酬が安い税理士の選び方

税理士業界も、従来のような、記帳代行や税務申告などのルーティンワークだけをこなしていればOKな時代ではなくなってきています。
とはいえ、他の業界に比べるとまだまだ「サービス業」とは言いきれていないのが実態です。
しかし、その中でも「金儲け主義」ではなく誠実に対応してくれる税理士も着実に増えてきています。
税理士業界は「クレーム産業」というくらいクレームが多い業界なのです。
「税理士選びに失敗した。」と感じたら、どんどん税理士を変えて行きましょう。
それができる時代になってきました。
大きい税理士事務所だから安心?
職員数は多くいるのですが、料金に合わせて知識も経験も少ない新人が担当することが多く、適切なアドバイスを受けることができません。
また、横領防止やお客様との癒着を防ぐために定期的に担当者変更が行われます。
担当職員の年収は、顧客からの費用で決まるので、顧問料金が安いままであれば、いつまでも新人しか担当に付かないということもあります。
税理士報酬が安い税理士の探し方
きちんと質を担保した上で、税理士報酬が安い税理士を探す方法としては、
ネットからホームページを見ながら、税理士事務所を確認していく事もできますが、
どこも、似たような美辞麗句が並んでいて、正直違いがよくわかりません。
それに、問合せをしたら契約をしなくてはいけないのか不安になります。
そんな時は、税理士紹介サービスがおすすめです。
希望する条件の税理士を、こちらが納得するまで無料で何人でも紹介してくれます。
もちろん、希望する条件に合う税理士が見つからなくて契約をしなくても、費用を請求されることはありません。
税理士紹介サービスの中でも「コスト削減税理士」に強い税理士紹介サービスを紹介します。
「コスト削減税理士」に強い税理士紹介サービス
税理士ドットコム
おすすめな税理士紹介サービスは「税理士ドットコム」です。
あなたが希望する条件に合った税理士を、迅速に紹介してくれます。
早い時には、相談したその日に紹介して貰えることもあります。
断る時は、税理ドットコムのコーディネーターが断ってくれるので、あなたが気まずい思いをすることもありません。
上場会社が運営しているので信頼感があり、登録税理士数や紹介マッチング件数は業界最多です。
登録税理士が多いので、1回の相談で4〜5人の税理士は紹介してもらえます。
1回の相談で20人の税理士と面談したという強者もいるそうです。
税理士報酬は利用者の70%以上の人が下げることができています。
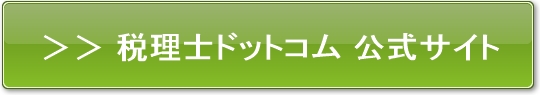
【関連記事】税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
税理士紹介センタービスカス
税理士紹介サービスのパイオニアで運営歴は27年と業界最多です。
ホームページにも税理士報酬削減の事例が掲載されています。
累計相談件数15万件以上、利用満足度98.3%の実績があります。
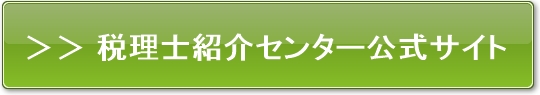
【関連記事】 税理士紹介センタービスカス 評判
税理士紹介ラボ
税理士報酬の削減にこだわっている税理士紹介サービスです。
もちろん、安かろう悪かろうではありません。
税理士の質も税理士ラボが責任を持って対応しています。
税理士紹介ラボは、保険会社などの比較サイトを運営していて、比較して費用を見直すノウハウにはかなりの実績があります。
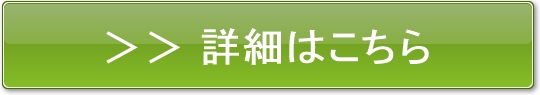
【関連記事】 税理士紹介ラボの評判、口コミ!税理士報酬を削減するならおすすめ
ベンチャーライフ税理士紹介
信頼できる費用が 安い税理士を紹介してくれる税理士紹介サービスです。
ここで紹介してくれる税理士は全員が決算料0円で、毎月の顧問料1万円から引き受けてくれます。
ベンチャーライフでは税理士選びで、料金を交渉する必要はありません。
全員が、下表のように決められているからです。
◆税理士報酬◆
|
年間売上高 |
月々 |
決算料 |
年間 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 10,000円 |
0円 |
120,000円 |
| 3,000万円 | 15,000円 |
0円 |
180,000円 |
| 5,000万円 | 220,000円 |
0円 |
240,000円 |
| 1億円 | 30,000円 |
0円 |
360,000円 |
| 1億円超 | 応相談 |
0円 |
応相談 |
このように料金が売上に応じて明朗会計になっています。
激安だからといて、業務に手抜きがあるのではありません。
次の業務を料金内でこなしてくれます。
|
・来所又は訪問での相談 |
・消費税申告書の作成 |
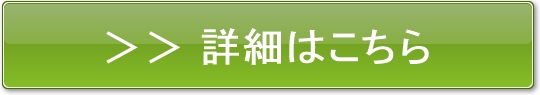
【関連記事】ベンチャーライフ 評判!税理士の顧問料 月1万円〜。決算料0円
税理士選びで一番大事なのは、税理士と面談して相性が合うかどうか確認することです。
相性が合うとは、「なんでも相談することができるかどうか」が判断材料になります。