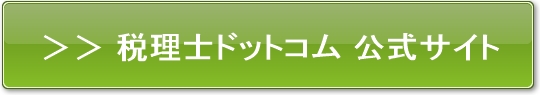![マイクロ法人 税理士 費用]()
この記事では、マイクロ法人の税理士費用について紹介しています。
マイクロ法人の税理士費用は、以前は月額5、000円が一番の格安でしたが、現在は月額1,000円〜が相場となっています。
とにかくマイクロ法人の節税効果はすごいです。
社会保険料を最安にしたり、極端ですが、所得税、住民税を0円にすることも可能です。
できれば、法人化設立の手間や、設立後の確定申告を考えると、立ち上げから専門の税理士に頼んでまかせたいものです。
しかし、設立の経費や税理士の費用が節税効果より上回れば設立する意味がありません。
節税効果については表などを使って詳しく説明しているので参考にしてみてください。
また、マイクロ法人には節税効果だけでなく、数多くのメリットがあります。
マイクロ法人設立のメリットとデメリットも紹介しています。
しかし、マイクロ法人は違法となるケースもあるので、違法になるケース、違法にならないための対策も説明しているので、よく確認はしてください。
マイクロ法人 税理士費用
法人の決算書の作成や、確定申告のスポット依頼なら、税理士の費用は、安くなります。
相場は、
10万円〜20万円です。
この場合、自社で会計ソフトの入力、帳票、書類の整理をする必要があります。
すべて(税務相談、記帳代行や給与計算、年末調整、異動届の提出など)を税理士に丸投げする場合の費用相場は
年/20万円〜30万円です。
マイクロ法人 税理士費用 相場
記帳代行は、月額ではなく仕訳1件につきいくらと料金設定しているところもあります。
マイクロ法人の税理士費用の実例
マイクロ法人の税理士費用は、前述したように様々ですが、実例をいくつか紹介します。
税理士ドットコムに寄せられた約10万件の相談実績の中から、資産管理会社などマイクロ法人を運営している方の料金実例です。
◆実例1)
売上高400万円/不動産業
年間顧問料
18万円
(顧問料に加え、決算申告・年末調整料込み)
複数の賃貸不動産を所有し、記帳代行は利用しなくて自分で記帳。
◆実例2)
売上高1000万円/資産管理
年間顧問料
25万円
年齢が近いこと、会える距離である事の条件で税理士を変更
◆実例3)
売上高3000〜5000万円/株式投資
年間顧問料
36万円
個人で保有している株式を、資産管理会社を設立してそちらに移動。
資産管理会社の運営や出資について詳しく、税務上のアドバイスをしていただける税理士と契約。
*参照元:税理士ドットコム HP
税理ドットコムに最短30秒で、より詳しく無料で問合せすることができます。
![マイクロ法人の税理士費用]()
マイクロ法人 税理士いらず
マイクロ法人は税理士いらずでも運営できますが、初年度はかなり大変です。
できれば、法人化の立ち上げから1年目は税理士に相談しながら進めて、
2年目以降に状況に応じて自力で進めるのが効率的です。
マイクロ法人の運営の知識は、ネット上で取得することができます。
ただし、情報が古かったり、専門家ではない人の発信もあるので注意が必要です。
確実なのは、ネット情報を鵜呑みにしないで、必ず行政の公式サイトで最終確認をすることです。
手間はかかります。
税金や申請まわりの情報は簡単に調べられますが、
各種補助金や出張旅費手当、社宅など法人の運営に必須ではない制度については調べようがありません。
これは税理士と契約していないデメリットといえるでしょう。
もう一つ税理士と契約していない、大きなデメリットは、
書類の作成や申告の作業の面倒くささです。
法人の運営に必要な書類や申請は個人事業主とは比べられない多さです。
会計の入力は個人事業主と同じようにクラウド会計ソフトの
freeeや
弥生会計で簡単に処理できますが、
年末調整はやることが増えます。
所得の源泉徴収票等の法定調書、給与所得の源泉徴収票、基礎控除申告書等々用意するものがかなり多いです。
さらに法人決算・法人税申告はかなり難しいです。
書類枚数、記入事項が多く、参照する数字を探すのもとても面倒です。
ネット上で検索しても体系的な情報がまとまっていません。
マイクロ法人の税理士を探す
マイクロ法人で税理士を探すのなら、最も手軽で確実な会計事務所、税理士紹介サービスを紹介します。
税理士ドットコム
税理士紹介サービスは数多くありますが、その中でも前述の「マイクロ法人の税理士費用の実例」で紹介したように、
マイクロ法人の税理士紹介で、最も実績がある税理士紹介サービス「税理士ドットコム」を紹介します。
「税理士ドットコム」には、マイクロ法人に関する税務相談も数多くよせられています。
これらの相談に税理士が無料で解答していているのですが、あなたもこれらの相談を閲覧することができます。
また、自分の状況を相談することもできます。
無料です。
こちらから、80件以上のマイクロ法人についての相談を確認することができます。
↓マイクロ法人の税理士選びはこちら↓
![マイクロ法人 税理士費用]()
【関連記事】 税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
マイクロ法人とは
![マイクロ法人の税理士費用]()
ご存知だとは思いますが、簡単にマイクロ法人について説明します。
マイクロ法人とは、株主と取締役が一人の小さな会社、もしくは身内だけで運営している会社のことです。
プライベートカンパニーとも呼ばれることもあります。
一人社長が従業員を雇わない事業形態です。
規模の拡大を目的としません。
通常の株式会社などのように利益を追求することが目的ではなく、節税を目的とします。
個人事業はそのままで、別にマイクロ法人を設立します。
個人事業主のための法人がマイクロ法人です。
マイクロ法人 節税効果
![マイクロ法人 税理士 費用]()
節税できる税金
- 社会保険料の減額
- 所得税の節税
- 住民税の減額
- 消費税の免税
節税効果、減額効果は設立年度だけでなく、設立後も毎年、節税・減額することができます。
社会保険料の減額
個人事業主の保険は国民健康保険と国民年金ですが、マイクロ法人を設立し、マイクロ法人から給料を受け取ることで、公的保険が健康保険と厚生年金に切り替わります。
マイクロ法人から受け取る給料を少なくすれば、社会保険料を減らすことができます。
年収400万円の事例
このメリットは扶養者が増えるほど効果を発揮します。
社会保険加入者は、被扶養者(配偶者・子ども)の国民年金と健康保険料支払いが不要になるからです。
所得税の節税
法人と個人でそれぞれ1億円の利益を出した場合の税金
- 個人事業主:約5,500万円(1億円×55%)
- 法人:約3,500万円(1億円×35%)
1億円の利益で考えると
2,000万円も税金が節税できます。
法人から受け取る給料は、最低額55万円の給与所得控除が適用されます。
つまり一旦法人を経由して、給料収入という形にするだけで、所得を55万円減らすことができるのです。
あわせて住民税も節税できます。
極端ですが、給与所得を年間55万円にすれば、給与収入55万円−給与所得控除55万円で0円となるため、
所得税・住民税も発生しません。
配偶者や子供を法人の役員にすれば、役員報酬・賞与を払うことができ所得分散効果も得られます。
稼いでいる人ほど、所得税の税率が高くなるので節税額は大きくなります。
個人事業主として青色申告で最大65万の控除に加えて、マイクロ法人として最低55万の給与所得控除をダブルで受けることができるのです。
消費税の免税
消費税の免税効果は、令和5年10月にインボイス制度が導入されるため薄れるかもしれません。
売上1000万円を超えると、その翌々年から消費税を払わないといけません。
しかし、売上の一部をマイクロ法人に移すことで、売上を1000万円以内に抑えていれば、消費税が免除になる可能性があります。
マイクロ法人は違法?
マイクロ法人で節税すること自体は違法ではない
マイクロ法人で節税すること自体は違法ではありません 。
個人事業主がマイクロ法人を設立することも、マイクロ法人と個人事業主の二刀流にすることも、自由に行えます。
ただし、マイクロ法人で節税するためには、いくつかの注意点があります。
例えば、マイクロ法人の事業内容や経営状況をしっかりと証明できることや、個人事業主とマイクロ法人の事業内容を明確に区別できることなどです。
これらの注意点を守らない場合は、マイクロ法人が違法になる可能性があります。
その場合は、重い罰則や追徴課税などのリスクに直面することになります。
マイクロ法人で違法になるケースとは何か?
マイクロ法人で違法になるケースは主に以下の3つです 。
- 個人事業主とマイクロ法人が同じ事業を行う場合
これは、「個人事業者から収入を隠してマイクロ法人に移す」という行為とみなされます。
所得隠しや脱税行為として処罰される可能性があります。
- マイクロ法人がペーパーカンパニーになる場合
これは、「実態のない架空の会社」という意味です。
ペーパーカンパニーは、節税目的だけで設立されたり、実際に事業活動を行わなかったりします。
不正会社や偽装会社として摘発される可能性があります。
- マイクロ法人が社会保険料を不正に安くする場合
これは、「個人事業者から収入を隠してマイクロ法人の給与や配当に移す」という行為とみなされます。
社会保険料の不払いや逃れ行為として処罰される可能性があります。
マイクロ法人で違法にならないための対策
個人事業主とマイクロ法人の事業内容を明確に区別する
マイクロ法人で違法にならないためには、まず、個人事業主とマイクロ法人の事業内容を明確に区別することが必要です。
例えば、個人事業主はコンサルティングや執筆などのサービス業を行い、マイクロ法人は商品の販売や開発などの製造業を行うというように、異なる業種や業態にすることが望ましいです。
また、個人事業主とマイクロ法人の間で取引を行う場合は、市場価格や相場に基づいて適正な金額を支払うことが重要です。
これは、個人事業主からマイクロ法人への利益移転や逆移転を防ぐためです。
マイクロ法人の実態や経営状況をしっかりと記録する
マイクロ法人で違法にならないためには、次に、マイクロ法人の実態や経営状況をしっかりと記録することが必要です。
例えば、マイクロ法人の事業計画や目標、収支や財務状況、取引先の情報などを定期的に作成し、保存することが望ましいです。
また、マイクロ法人の活動内容や成果物、契約書や領収書などの証拠資料もきちんと整理し、保管することが重要です。
これは、マイクロ法人がペーパーカンパニーではなく、実際に事業活動を行っていることを証明するためです。
マイクロ法人の社会保険料を正しく計算する
マイクロ法人で違法にならないためには、最後に、マイクロ法人の社会保険料を正しく計算することが必要です。
例えば、マイクロ法人の給与や配当は所得税や住民税の対象になりますが、社会保険料の対象にはなりません。
これは、給与や配当が「報酬」としてではなく、「利益分配」として扱われるためです。
しかし、給与や配当が「報酬」として扱われる場合もあります。
これは、「給与や配当が事業活動に必要不可欠である」と判断される場合です。
この場合は、「報酬」として社会保険料の対象になります。
したがって、マイクロ法人では、「報酬」と「利益分配」の区別を明確にし、「報酬」に対して社会保険料を正しく計算し支払うことが重要です。
これは、社会保険料の不払いや逃れ行為を防ぐためです。
マイクロ法人 メリット
マイクロ法人のメリットは、上記で説明した節税が一番ですが、
その他にも次のようなメリットがあります。
欠損金を10年間繰り越せる
事業が赤字だった場合、個人事業主は欠損金を繰り越しできるのは3年間ですが、
マイクロ法人は10年間の繰り越しができます。
「代表取締役」の肩書が使える
マイクロ法人は、社員が1人もいなくても「代表取締役」を名乗ることができます。
社長の肩書を使用することで、対外的信用力も上がり、新規顧客の獲得もしやすくなる可能性が高まります。
事業を成長させるためにもとても有益です。
合同会社の場合は「代表社員」になりますが、基本的な意味は同じです。
経費に計上できる範囲が広がる
生命保険、医療保険 控除の上限がない
個人の生命保険料控除は最大12万円という上限がありますが、法人で生命保険に入れば上限はありません。
自宅の家賃を経費に計上できる
自宅を事務所として使う場合、事務所利用分は経費に計上することができます。
例えば家賃20万円の賃貸を借りて、そのうち4分の1を事務所として使っていれば5万円を経費に計上できます。
出張手当を経費にできる
出張手当は、個人事業では認められていませんが、出張規程を作って出張報告書などを整備することで、
給与に加えられても給与課税がされません。
自家用車を経費にできる
個人所有の自動車でも事業に利用した場合は、自動車の減価償却費のほか、ガソリン代や自動車保険なども事業利用割合に応じて経費に計上できます。
マイクロ法人 デメリット
法人設立の費用・手間がかかる
会社の種類は「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類ありますが、マイクロ法人におすすめなのは「合同会社」です。
設立費用ですが、株式会社の場合は、最低約24万円、合同会社の場合は、最低約11万円がかかります。
マイクロ法人設立費用
税務申告の手間が増える
個人事業主とマイクロ法人の両方で確定申告が必要なので、確定申告の手間が2倍に増えます。
個人事業主なら1年に1回の確定申告ですみますが、マイクロ法人は、決算報告書のほかに、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの書類を提出する決算申告をしなければいけません。
マイクロ法人に税理士は必要?
まず、そもそもマイクロ法人を設立して税金の申告をする場合、税理士が必要か?ということですが、
1人会社であれば、経費処理がかんたんなので税理士無しでも大丈夫でしょう。
特にマイクロ法人の会社形態は合同会社を取ることが多いので、株式会社と違って、
株主や債権者に向けて、会社の経営状況や財務状態などを明示する決算公告義務もありません。
証券投資をメインとする一人会社であれば、分離課税がとられているので税理士の必要性はさらに少なくなります。
◆決算申告を自分で行う手順◆
- 取引内容を会計ソフトに入力
- 決算書類を作成
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(合同会社は社員資本等変動計算書)
個別注記表、計算書類の附属明細書、事業報告書、キャッシュフロー計算書、勘定科目明細書、総勘定元帳、領収書綴り
- 申告と納税
法人税申告書、消費税申告書(課税事業者)、地方税申告書、法人事業概況説明書、税務代理権限証書
- 経理・会計書類を保存(7年〜10年)
こうして見ると大変そうですが、ほとんどの書類、申告書は会計ソフトできます。
会計ソフトはマイクロ法人なら
「マネーフォワード」![]()
がおすすめです。
会社設立手続きも「マネーフォワード」が提供する
「クラウド会社設立ソフト」![]()
を使えば、
「株式会社」「合同会社」の設立なら無料で会社設立情報から、書類作成を自動で行ってくれます。
作成した書類の提出をいつ、どこに提出すればいいのかも教えてくれます。
どちらも無料で使うことができるのでおすすめです。
ただ、一人会社で投資業ではない事業を行っている場合は、役員報酬の設定、決算対策などにより税理士との顧問契約の必要性は高まります。
不動産投資の場合も、設備投資による税務の判断が必要となるため税理士との顧問契約の必要性が高まります。
マイクロ法人設立の手続きや設立後の決算申告も大変なのに、個人事業主の申告とダブル申告が必要になるので、実際に行うとなると、とても面倒です。
自分で出来ればいいのですが、できれば立ち上げから専門の税理士に頼んでまかせたいものです。
特に事業に集中したい方や、適切な節税対策や決算申告書の作成に自信がない方は、税理士に依頼することをおすすめします。
マイクロ法人の税務を税理士に依頼するメリット
マイクロ法人の税金申告を税理士に依頼するメリットは以下の通りです。
税務知識や会計スキルが不要
マイクロ法人の税金申告は、所得税や消費税などの種類や計算方法、確定申告書や決算書などの書類作成など、多くの知識やスキルが必要です。
しかし、税理士に依頼すれば、専門家に任せることができるので、自分で勉強したり悩んだりする必要がありません。
税務調査や納税相談のサポート
マイクロ法人は、確定申告書や決算書などの提出後も、税務署からの問い合わせや調査を受ける可能性があります。
また、納税方法や節税対策などについても相談したい場合があるかもしれません。
このような場合には、税理士が代わりに対応したりアドバイスしたりしてくれるので、安心です。
節税効果や経営改善の提案
マイクロ法人は経費の適切な計上などで節税効果を得ることができます。
しかし、自分で判断するのは難しい場合もあります。
そのような場合には、税理士が最適な節税方法を提案してくれます。
また、決算書や財務分析などから経営状況や課題を把握し、経営改善の提案もしてもらえます。
マイクロ法人の税務を税理士に依頼するデメリット
費用がかかる
マイクロ法人の税金申告を税理士に依頼する場合は、費用がかかります。
費用は、税理士や業務内容、契約形態などによって異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度です。
マイクロ法人は事業規模が小さいことが前提なので、費用対効果を考える必要があります。
自分で管理できない
マイクロ法人の税金申告を税理士に依頼する場合は、
税理士に任せることで自分で経営状況や財務状況を把握しづらくなる可能性があります。
税理士との相性や信頼性
マイクロ法人の税金申告を税理士に依頼する場合は、税理士との相性や信頼性も重要です。
例えば、税理士とのコミュニケーションや報告がスムーズかどうか、税理士が適切な知識や経験を持っているかどうかなどです。
このようなことを確認するためには、事前に紹介や口コミなどを調べたり、面談や相談したりする必要があります。
マイクロ法人 業種事例
メインの事業を個人事業主で、副業をマイクロ法人にします。
マイクロ法人は、ウーバーイーツ、せどりなど、個人事業主に向いていますが、他にもマイクロ法人に向いている業種も紹介しています。
ウーバーイーツは法人契約はないですが、出前館は法人契約できます。
この場合、マイクロ法人で出前館 個人事業主でウーバーイーツと同じ事業ですが分けることもできます。
個人事業×マイクロ法人
- タクシー運転手×マンション大家
- 不動産投資×ソーラーパネル発電
- 株投資×せどり
- ECサイト制作×ウエブデザイン
- せどり×ウーバーイーツ
- ITコンサル×イラストレーター
- 税理士×コンサル事業
- プログラミング業×マーケティング事業
- 不動産賃貸事業×不動産管理事業
- 店舗サービス×ECサイト販売
- エンジニア×コンサルティング
他の組合せ:個人事業×〇〇〇〇
〇〇〇〇に下の事例を組み合わせてみてください。
- マンション大家
- ブログ(アフィリエイト)
- せどり
- 動画編集
- モデル
- フードデリバリー
- マッサージ・整体
- アプリ開発
- Webサイトの企画、制作、販売、運営及び管理
- Youtuber
- ITコンサル
- 不動産の保有、売買、交換、賃貸、管理及び運用
- 有価証券の保有、運用、管理、売買
- オンライン家庭教師
- ソーラーパネル発電
違法の可能性があるケース



![]()