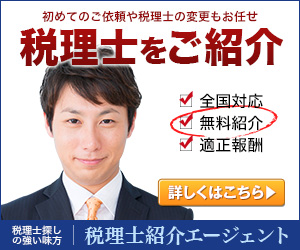本ページはプロモーションが含まれています。
月次決算書の作り方、月次決算のやり方を教えてくれる税理士

社会の変革スピードが時代とともに増す昨今、月次決算書は迅速な意思決定をするのに欠かせません。
月次決算は、法律上義務ではありませんが、変革スピードが早い社会情勢を反映して、多くの会社で導入がすすみはじめています。
とはいえ、初めて月次決算をしようと思うと大変です。
税理士に教えてもらえば簡単と思われがちですが、そうではありません。
月次決算書の作り方を教えてくれる税理士は誰でもいいわけではないのです。
その理由を説明します。
月次決算書の作り方を教えてくれる税理士
月次決算書の作り方を教えてもらうのに、税理士なら誰でもいいというわけではありません。
残念ながら税理士にも能力不足があり、税理士に依頼しても月次決算が導入しきれないことがあります。
その大きな原因は、社内の不整備もあるでしょうが税理士の力不足によるところも大きいです。
しっかりしている税理士なら、資料を受け取るだけで月次決算を作成してくれますが、多くの税理士はある程度の経理業務を会社に要求するからです。
税理士事務所のパワー不足で、月次決算書が1ヶ月遅れでできあがってきたりします。
それでは遅すぎるので、ある程度の業務をこちらに要求してくるのです。
自社で行う業務も、税理士が懇切丁寧に教えてくれればいいのですが、なかなかそこまで手取り足取りと行かないのが実情です。
しかし、伝票を渡すだけでスピーディーに月次決算をしてくれる税理士も数少ないですがいます。
伝票を渡すだけで記帳代行までしてくれます。
いわゆる丸投げですね。
しかし、いつまでも丸投げの状態では費用も増えてしまいます。
いい税理士なら、丸投げの状態から少しづつ社内がレベルアップするように、月次決算書の作り方を教えてくれます。
それにつれて、税理士への支払費用も減少するだけでなく、税務知識も社内に蓄積されます。
そんな税理士は、あなたの会社の成長に貢献してくれることでしょう。
月次決算を自社で行なう
月次決算を依頼すると費用がかかるので、自社で行うという方法もあります。
月次決算のやり方を説明します。
月次決算のやり方
月次決算は、作業が多いですが、具体的なフローを順番に紹介します。
- 残高の確認
現金預金残高と銀行残高を照合し、差異がないか確認します。
差異がある場合は、修正処理を行います。 - 月次棚卸高の確定
在庫金額を確定します。
帳簿と棚卸資産が一致するかどうか確認します。 - 仮勘定の整理
正確な金額がわからない支出や収入を一時的に記録する仮勘定を整理し、正しい勘定科目に振り替えます。 - 経過勘定の計上
費用が発生したタイミングで把握する発生主義を原則とし、支払いのタイミングと費用発生のタイミングが異なる場合には、前払費用や未払費用の勘定科目を使用して経過勘定を計上します。 - 減価償却費・退職給付費用の計上
年間の費用として期末に計上します。
月次決算で減価償却費や退職給付費用を計上して、正確な経営状況を把握します。 - 月次試算表の作成
月次決算の結果を確認するための試算表を作成します。
勘定科目の残高のみを記載する残高試算表や貸借それぞれを記載する合計試算表、両方を記載した合計残高試算表などがあります。 - 月次業績報告
月次試算表を基に、業績報告書を作成し、経営の進捗状況を把握します。
月次業績報告は、経営陣や関係者に提出し、経営戦略の調整や問題点の把握に役立てられます。
月次決算 作り方のポイント
月次決算の作り方のポイントは、会計ソフトの「仕訳パターン登録」機能を活用することです。
最初の仕訳パターンの登録さえ間違わなければ、いつも同じ仕訳をすることができるので、人為的なミスが無くなります。
どこの会社もそうですが、日々の取引の95%はパターン化できます。
残り5%はイレギュラーな取引なので、都度、税理士に質問することで、
自社で記帳ができるようになります。
会計ソフトは、ほとんどが1年間は無料で使えるので、試してみるといいでしょう。
適切な月次決算を実施するための、いくつかのポイントを紹介します。
- 経費精算の締め日を厳守
請求書や納品書、精算伝票などの書類は期限までに提出できるように、締め切り日を周知しておきます。 - 月次決算スケジュールを社内で共有
全社員が月次決算のスケジュールを把握し、自分の仕事と直結していることを理解することで、報告や書類提出のタイミングを意識して取り組むようになります。 - クラウド型システムを活用
経費や会計のシステムをクラウド化して、入出金データをリアルタイムで把握することができます。
さらに、クラウドにすることで他部門への報告業務も一斉に行えるため、短時間で情報共有して月次決算に反映させられます。
月次決算を税理士に依頼する
月次決算を自社で行うのは多忙な実務の中で、どうしても難しい場合があります。
そんな時には、税理士に月次決算を依頼してみてはどうでしょう。
いい税理士に巡り合えば、税理士は豊富な知識と経験を持っているため、正確かつスムーズな月次決算を行うことができます。
さらに、税理士に依頼することで、自社の経営に関するアドバイスや、節税のアドバイスを受けることもできます。
ただし、税理士に依頼する場合には、事前に費用やサービス内容、納期などをしっかりと確認しておくことが大切です。
経営において月次決算は非常に重要な作業です。
自社で行うのが難しい場合は、税理士に依頼することもぜひ検討してみてください。
あなたの会社の税理士はどうですか?
決算処理はしてくれるけれど、納税額を申告直前にしか教えてくれなかったり、
月次決算書は作成してくれるけれど、作成に1ヶ月もかかり、
作成されたと思ったら月次決算書だけをポンと置いていき、
何も説明がない税理士ではありませんか?
正直、会社の業績を伸ばそうと思ったら月次決算をおろそかにする税理士では会社の成長に貢献することはできないでしょう。
あなたの会社の税理士が月次決算の作り方を懇切丁寧に教えてくれればいいのですが、
そうでないのなら思い切って会社の成長に貢献してくれる税理士に切り替えるタイミングかもわかりません。
税理士を変更するしないは別にして、まずは、税理士紹介サービスを通じて、複数の税理士と会ってみてはどうでしょう?
質重視の税理士紹介サイト
税理士紹介サービスにも、それぞれ特徴があります。
- 「コスト削減税理士」に強いサイト
- 「質重視の税理士」に強いサイト
- 「若手税理士」に強いサイト、
などに分かれているのですが、
月次決算を依頼するのなら「質重視の税理士サイト」から税理士を探しましょう。
「質重視の税理士サイト」を3つ紹介します。
税理士紹介エージェント
税理士がWEB上で申請すれば、誰でもが登録される税理士紹介サイトと違います。
税理士紹介エージェントは、経理経験豊富な担当者が、
一人ひとり税理士と直接面談し、経歴、専門分野、実績、知識、人柄、考え方などをしっかり確かめ、「お客様最優先」という理念に合う税理士さんだけを少数精鋭で登録しているのです。
【関連記事】税理士紹介エージェントの評判、口コミ。税理士は質重視の少数精鋭
税理士紹介ネットワーク
高齢の税理士が多い中、税理士紹介ネットワークは若手税理士中心に登録されています。
税理士紹介ネットワークも、専門性のみならず、姿勢まで含めた厳正な審査を通過した税理士のみを紹介しています。
若い税理士は、比較的顧問料が安く、気軽に相談しやすく態度が謙虚な人が多いです。
また、気力にあふれ、熱心に対応してくれます。
![]()
【関連記事】若い税理士を探すなら、おすすめは日本税理士紹介ネットワーク!
税理士ドットコム
税理士紹介サービスの最大手です。
税理士登録数、相談件数、紹介実績、どれをとっても業界最多です。
運営経歴が17年以上と長く、上場会社が運営していることも信頼がおけます。
税理士費用も面談をする前に、概算の見積りを貰うことができます。
事前に料金を見比べて税理士を比較検討することが可能です。
従業員を雇うのと同じように、何人も面接して、よさそうな人をじっくり選べる環境が整っています。
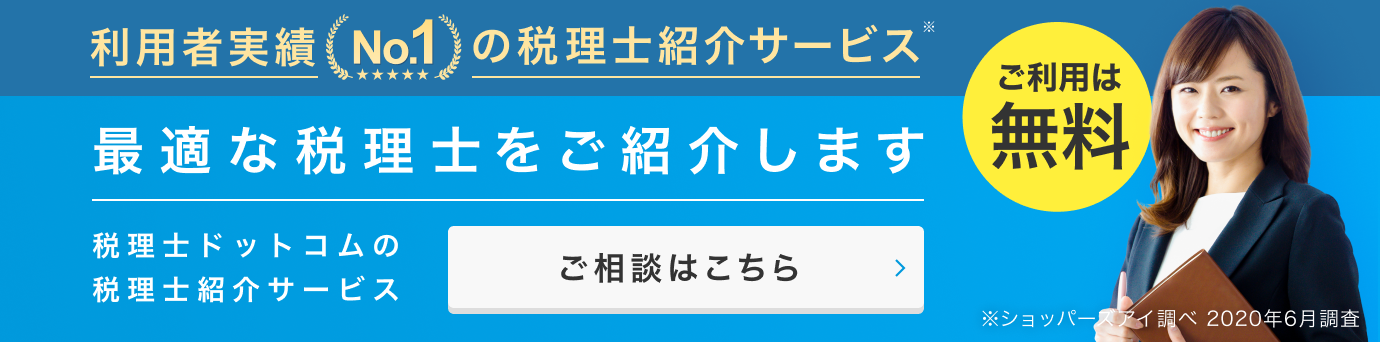
最短当日|24時間受付|年中無休|全国対応
【関連記事】 税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
税理士紹介サービスは、紹介した3社以外にもたくさんあります。
こちらで20社をランキング比較しています。
3社以外もいろいろ確認したいという方は参考にしてみてください。
月次決算の目的
月次決算は、毎月ごとの収支を正確に数字で表すことが目的です。
前述したように、その月に売上が上がっても、入金は現金もあれば、翌月あるいは三ヶ月後と取引先によって異なる場合があります。
入金されるまで売り上げに計上しないと、その月に会社が儲けた正確な金額がわかりません。
ですので月次決算では未収金や売掛金という勘定科目を使って計上します。
支払の場合も、その月に仕入れ(債務)が発生しても、支払いをするのは翌月以降ですよね。
しかし債務が発生しているので、仕入れも未払い金や買掛金として計上します。
こうすることで、その月に発生した会社の売り上げや支払いを正確に出すことができるのです。
他にも、従業員給料の所得税等の預り金や社会保険の法定福利費などもきちんと計上されます。
月次決算でわかる分析資料

- 損益計算書および貸借対照表
- 損益の推移表
- 資金繰表
- 借入金管理表
- 部門単位の損益計算書
- 部門単位の損益の推移表
- 得意先別、商品別の売上高推移表
- 経費管理表
- 売掛金残高表および買掛金残高表
- 在庫管理表
- 各種経営指標
売上総利益率、営業利益率、経常利益率、流動比率、固定比率、自己資本比率、売上債権回転率、棚卸資産回転率、損益分岐点比率、商品別貢献利益率 など
月次決算を作成するメリット
- 経営状態を早く把握することができる
- 予算の達成が実現しやすくなる
- 投資の判断がタイムリーにできる
- 資金繰り表を作成し資金繰り対策ができる
- 売掛債権の確認ができる
- 節税対策ができる
- 銀行からの信用力がアップする
などなどです。
一つづつ詳しく説明します。
経営状態を早く把握することができる
1年を終わってみないと会社が儲かっているのか、儲かっていないのかがわかるのと、
毎月の営業成績や財務状況が数値で把握でき分析できるのとでは、大きな違いです。
月次決算を出すことで問題点の把握、原因分析、対策・立案がより迅速にできます。
財政状態が悪化していれば早めに食い止めて業績向上につなげることもできます。
予算の達成が実現しやすくなる
毎月の営業成績が把握できることで、予算との差異が明かになり、未達成の時には早めに対策を打つことができます。
投資の判断がタイムリーにできる
情報社会の今の時代に、1年の決算を待って投資するかしないかを決めていては遅すぎます。
月次決算で、売上が前年比〇〇パーセント伸びて、生産量も〇〇パーセントアップしているという情報が確認できれば、増員、設備投資などの判断がくだしやすくなります。
資金繰り対策
前述したように、売上が上がっていても、入金とのタイムラグがあれば短期的な資金ショートも起こることがあります。
月次決算を行うことで資金繰り表も作成されるので、毎月の現金の過不足を把握することができます。
それにより、売上債権の入金・回収と仕入債務の支払いなどの調整が可能になります。
状況によっては銀行に、つなぎ資金を早めにお願いすることもできます。
売掛債権の確認
売上が増えるのに比例して債権が増えるのは問題ないのですが、そうでない場合は問題です。
月次決算を作成することで、売上債権回転率や売上債権回転期間などの分析資料も作成されるので、回収の遅延といった状況の分析ができ、早急な対策を実行することができます。
節税対策
月次決算を行うことで、計上すべき費用の漏れがなくなり、余分な税金を払うことが無くなります。
また、早めに会社の業績がわかると、決算賞与や社内旅行、設備投資など適切な費用計上で利益を減少させ節税することができます。
銀行からの信用力がアップ
金融機関から融資を受ける時には過去三ヵ年の決算資料だけでなく、最新の月次決算書(試算表)を求められることがあります。
その時に、すぐに試算表を提出することで、銀行から御社への財務管理面での評価が高まり、融資も受けやすくなります。
月次決算のデメリット
今まで、メリットで取り上げてきたことが全て享受できないことです。
月次決算を自社で行おうとすれば、社内での混乱やトラブルも予想されますが、税理士に丸投げならする方法もあります。
もちろん、税理士への費用は発生しますが、月次決算を取り入れたことのメリットと天秤にかけてみてください。
月次決算を取り入れることで、社内の管理レベルも徐々にステップアップしていくはずです。
月次決算と年次決算の違い
年次決算の実施は法律で義務づけされていますが、月次決算は任意で行われるもので義務付けはされていません。
月次決算は、毎月の業績や財務状況を正確に把握することと、
年次決算の業務負担を軽減することです。
年次決算は厳密な正確さが求められ、年次決算にもとづいて確定申告と納税を行います。
提出期限が決められているので、法人なら期末の翌日から2ヵ月以内、
青色申告なら翌年2月16日から3月15日までの間に行います。
月次決算と試算表の違い
月次決算と試算表に違いはありません。
呼び名が違うだけです。
月次決算書は、月次試算表、残高試算表とも呼ばれ、貸借対照表と損益計算書の2つの財務諸表で構成されています。
月次決算書は、たんに作成すれば良いというものではなく、
減価償却費と棚卸残高の計算(計上)は省略せずに、適正な会計ルールに基づいて毎月行った方が良いでしょう。
省略することで、利益計算が不正確になり、経営の決断ミスや資金繰りの失敗リスクを高めます。
資金繰りの勘違い、間違い

損益計算書で利益が出ているのに手元に残っていない。
会計上、ほとんどの場合、損益計算書と手元の現金は一致しません。
それは、損益計算書が発生主義だからです。
つまり、売上は入金が無くても売り上げが発生したときに計上します。
経費も同じように、代金を支払ったかどうかは関係なく仕入れた時に計上します。
極端ですが、売上が発生から1ヶ月後の入金で、経費が現金払いだとしたら、仮の数字で例えるとこんな感じになります。
- 損益計算書:売上100万円ー経費70万円=利益30万円
- 資金繰り表:売上0円ー経費70万円=手元現金▲70万円
損益計算書では利益が30万円増えているのですが、現実は70万円も資金が不足しているのです。
この傾向のままだと、売上が伸びれば伸びるほど売掛金や在庫も増えていくのでますます資金繰りが悪化していきます。
最悪、黒字倒産も考えられます。
借入の返済額を忘れている
損益計算書の話をしましたが、そこに銀行への返済があったらどうなるのでしょう?
銀行への返済は経費ではないので損益計算書に計上しません。
つまり、10万円の銀行返済があったとすると、実際の手元資金の不足は70万円+10万円=▲80万円にもなるんです。
銀行への返済は借りたものを返しているだけなので、経費にはならないんです。
銀行から借り入れをした時に収入として計上もしていないので当然ですよね。